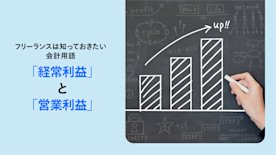![]() Squareガイド
Squareガイド1分でわかるSquareのアカウント作成
![]() Squareガイド
Squareガイド5分でわかるSquareの使い方【決済端末編】
![]() Squareガイド
Squareガイド5分でわかるSquareの料金体系
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識ドミナント戦略の実践のポイントとは?国内5社の成功事例やメリット・デメリットを解説
ドミナント戦略とは、飲食や小売りなどのチェーン店の戦略的な出店方法の一つです。そのメリットやデメリットを、5社の事例と共に確認していきましょう。ネットビジネスにも応用可能な、ドミナント戦略実践のためのポイントも解説します。
![]() 法律・税金
法律・税金風営法とは?バーや居酒屋の開業時のポイントを解説
バーなど深夜にお酒を出すお店を始めるには、風営法に注意しなければなりません。営業時間や違反にならないための要点、改正の内容を解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識ノーショー (無断キャンセル)とは?キャンセル防止対策をご紹介
経営者の悩みの種、ノーショー問題を徹底解説。ノーショーが起きる背景や対策、効果的なキャンセル料設定方法も詳しく紹介します。
![]() Eコマース
Eコマース受け取り拒否の商品、送料は誰が負担?ネットショップの正しい対応、法的措置は?
ネットショップが発送した商品が受け取り拒否をされた場合、購入者に送料を請求することは可能なのでしょうか。代金引換(代引き)や後払い決済による取引で起こりえる、受け取り拒否の問題の対策や法的措置について解説します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレスホテル・宿泊施設にオススメのPOSレジアプリ5選 - Square
POS機能を搭載したPOSレジは、売り上げに関する情報を収集できる便利なレジです。そこで今回は、宿泊施設経営者オススメのPOSアプリを厳選して紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレスキャッシュレスで会計を効率化!イベント出店の大きな味方、モバイル決済
イベント出店時のキャッシュレス決済導入でレジまわりの業務を楽に。キャッシュレス決済対応のメリットや注意点、おすすめの決済端末を紹介します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識後払いとは?導入時の注意点やメリット、デメリットを解説
後払いは、商品を受け取った後に支払う決済方法です。後払いの具体的なメリット・デメリットを掘り起こしながら、導入方法まで解説します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス音楽フェスもキャッシュレス時代!導入のメリットと方法を解説
サマソニやフジロックなどの音楽フェスでキャッシュレス決済が急増中!主要フェスでの最新決済事情や出店者・店舗向けにメリットや導入方法を紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス実店舗にクレジットカード決済を導入するメリット
現金、クレジットカード決済、電子マネーなど支払い方法が多様化している現代。事業者はお客様のニーズに柔軟に合わせて対応することが求められています。今回は居酒屋やカフェ、ネイルサロンなど実店舗を経営する人に向けて、カード決済を導入するメリットについて紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレスQRコード決済とクレジットカード決済を比較!どっちを導入するべき?
QRコード決済とクレジットカード決済の違いや、それぞれのメリットを解説し、店舗運営者におすすめの決済サービスを紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス飲食店でキャッシュレスを導入するメリットとは
利用者が増えているキャッシュレス決済。飲食店でキャッシュレスを導入するメリットや注意点、おすすめのキャッシュレス決済端末を紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス家賃集金は口座振替よりもクレジットカード決済!空室対策にも
家賃集金において、口座振替よりも多くのメリットがあるクレジットカード決済の特徴や導入方法、注意点について分かりやすく解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識キャンセル料金の請求に必要なキャンセルポリシーとは?書き方と例文、伝えるコツ
キャンセルポリシーの書き方のコツをご存知ですか?基本を押さえたキャンセルポリシーの書き方や例文を紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス業種別のPOS連携を9例紹介!おすすめはキャッシュレス決済とのPOS連携
業種別のPOSレジ連携を9例を紹介します。POSレジとキャッシュレス決済端末を別々に運用しているという店舗に向けて、Squareと連携可能な各社サービスをご案内しています。
![]() キャッシュレス
キャッシュレスCAT端末とは?利用のメリットやモバイル決済との違いを解説
電子マネーやモバイル決済、クレジットカード決済など、世界各国でキャッシュレス化が進んでいます。国内のニーズへの対応だけでなく、増加する訪日外国人客にも気軽に店舗に来てもらうためも、ぜひ導入したいのがクレジットカード決済です。店舗でカード決済に対応するためには、加盟店契約のほか、決済に対応する端末が必要です。カード情報を読み取る決済端末、CAT端末とはどんなものなのか、紹介します。
![]() 開業のヒント
開業のヒント駐車場経営は儲かるのか?初期費用や収入モデル、成功のポイントを解説
土地活用で人気の駐車場経営。初期費用が低いなどのメリット、ビジネス運営上のデメリットなど失敗しないために押さえておきたいポイントを解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識海外出張の際にあると役立つ!必須&オススメ持ち物17選
海外でのミーティングや商談、視察、リサーチなど、海外出張の機会がある人も多いでしょう。法律や文化、生活様式の違う外国での滞在には、万全な準備で赴きたいものです。今回は、海外出張前の荷造りについてチェックポイントを解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識飲食店でセルフオーダーを導入するメリットや方法を解説
注文受付からお会計までを自動化できるセルフオーダー。この記事では、セルフオーダーシステムの導入方法、費用、導入のメリットなどを解説します。
![]() Eコマース
Eコマース上代・下代とは?ネットショップ運営の小売専門用語まとめ
上代・下代など、ネットショップを始めるなら知っておきたい小売の専門用語を紹介。参考上代や掛け率といった関連用語もあわせて解説します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス運転代行サービスにカード決済導入をしたほうがいい理由とは
お酒を飲んで車が運転できない、でも家に車で帰らないといけない。そんなときに役に立つのが運転代行サービスです。運転代行サービスがキャッシュレス決済、なかでも主要な決済方法であるクレジットカード決済を導入する際のメリットについて紹介します
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識2店舗目の出店を考える飲食店が知っておきたいこと
1店舗目の飲食店が順調に売り上げを伸ばし、そろそろ2店舗目を出店しようかと考える経営者もいることでしょう。しかし、多店舗経営を効率よく運営していくには、メリット・デメリットを把握したうえで、成功するためのポイントをおさえておくことが重要です。今回は、2店舗目の出店を検討しはじめた飲食店経営者に向けて、知っておきたいことを紹介します。
![]() Eコマース
Eコマース個人販売サイトを作る方法と注意点
個人でネット販売を始めたい人や、ハンドメイド商品やアート作品などを販売するネットショップをはじめたいという人向けに、個人販売サイトを作る方法と注意点を紹介します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識飲食店におすすめのPOSレジ6選!POSレジの導入メリットや選び方も解説
スマートフォンやタブレットを利用したPOSレジを導入を検討している飲食店経営者に向けて、オススメPOSレジ8選を紹介します。
![]() キャッシュレス
キャッシュレス電子マネー決済端末を導入したい!端末の種類や選び方
電子マネー決済端末の導入を検討している事業主に向けて、端末を選ぶときのポイントや導入方法について解説します。
![]() 法律・税金
法律・税金【2025年最新】飲食店が利用できる補助金・助成金・給付金とは
飲食店が利用できる国の補助金・助成金・給付金124選、地方自治体の制度、申請方法などについて分かりやすく解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識経常利益とは?営業利益や純利益との違い、計算方法を解説
経常利益は、その字面から難しい印象を受けるかもしれません。 本記事では、経常利益について、経常利益とは何かから始め、経常利益の計算方法、営業利益や純利益との違い、経常利益に関連する注意点をわかりやすく説明します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識口座振替(口座引き落とし)とは?振込との違いや導入方法
口座振替の仕組み、口座振込との違い、メリットやデメリット、簡単に導入する方法などについて分かりやすく解説します。
![]() 法律・税金
法律・税金【2025年】新規事業の立ち上げ・創業に使える補助金・助成金5選
補助金・助成金のメリット、新規事業の立ち上げ・創業に使える制度5選、創業後に役立つ制度3選、申請の流れや注意点まで解説します。
![]() 法律・税金
法律・税金税務署での確定申告などの相談内容は?電話や窓口での相談方法も
確定申告をはじめ、税務署で相談できる内容や手段、相談するメリット・デメリットや注意点までわかりやすく解説します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識個人事業主のIT導入補助金の申請条件は?パソコンにも使える?
個人事業主向けに、IT導入補助金の対象製品・サービスや補助率、申請条件、必要書類、申請方法、注意点まで分かりやすく解説します。
![]() 開業のヒント
開業のヒントクリーニング店を開業するには何をすればいいのか?
季節の変わり目はもちろん、仕事で忙しいときや、どうしても落ちない汚れがあるときなど、クリーニング店を利用する機会は多くあります。クリーニング店を開業する際に必要な手続きについて紹介します。
![Inventory management is an integral part of your business.]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識いまさら聞けない!?在庫管理の基本知識
在庫切れや過剰在庫を防ぐために、店舗経営者として徹底したいのが在庫管理です。在庫管理の基礎を学びたい店舗経営者に向けて、自店舗に適した在庫管理システムの選び方や、効率よく在庫を管理する方法を紹介します。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識英語の請求書の書き方を伝授。よく使われる英単語やフレーズも紹介
英語で請求書を書けるようになるための知識や便利なサービス、英語の請求書を送るときのビジネスメール例などを紹介します。
![]() 法律・税金
法律・税金フリーランスが加入できる社会保険とは?保険料やおすすめの保険を紹介
フリーランスが加入できる社会保険、その保険料や加入方法、健康保険料を抑える方法、フリーランス向けにおすすめの民間保険サービスなどを紹介します。
![]() Eコマース
Eコマースリンク決済とは?リンク型決済徹底比較|メール対応
手軽に使えるリンク型決済の使い方から各社サービス比較をわかりやすく解説します。ネットショップ事業に興味のある方は必見です。
![]() ビジネス基礎知識
ビジネス基礎知識Google カレンダーを飲食店や美容院の「予約システム」として活用するには?
Google カレンダーは、オンライン予約システムとして利用することが可能です。この記事では、低コストで導入しやすいGoogle カレンダーを使うメリット・デメリット、そしてその機能性や連携可能な外部の予約サービスについて解説します。
商いのススメ
Town Square
1/40ページ
1–39/1431記事を表示中