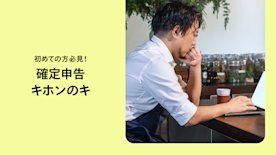※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
毎年2月になると確定申告書の受け付けが始まります。確定申告をする人の中には、初めて、もしくは久しぶりに確定申告を行うという人もいることでしょう。
本記事では、個人事業主やフリーランスの人を対象に、確定申告とは何かや、確定申告の基礎知識、確定申告の方法などについて説明し、最後に確定申告作業の負担を軽減するSquareのサービスを紹介します。
📝この記事のポイント
- 確定申告は毎年1/1〜12/31の所得と税額を確定し、原則翌年2/16〜3/15に申告・納付する手続き
- 個人事業主・フリーランスは、収入・経費・消費税などを自身で整理して申告し、納め過ぎがあれば還付を受けられる
- 申告の要否は収入状況により異なり、副業の所得が20万円超、給与収入が2,000万円超などの場合は申告が必要
- 申告にあたっては必要書類を準備のうえ、e-Taxまたは窓口・郵送で、定められた期限内に提出
- 申告方法は作成コーナー・申告ソフト・手書きなどがあり、Squareと会計ソフトの連携により作業負担を大きく軽減できる
目次
- 確定申告とは
- 確定申告の基礎知識
・確定申告関連で押さえておきたい単語
・確定申告が必要な理由
・確定申告の対象者
・必要な書類や事前準備、申告期限
・従業員がいる場合に必要な手続き
・確定申告について相談できる場所
・確定申告を税理士に依頼するといい場合 - 税金に関する基礎知識や疑問を解決
・個人事業主が納めるべき税金の種類
・法人税とは
・源泉所得税とは
・インボイス制度による変更点
・追徴課税とは - 賢く上手に節税対策
・控除制度を活用しよう
・家事按分を上手に活用
・ふるさと納税で税制メリットを享受 - 確定申告のやり方4選
・(1)確定申告書等作成コーナーを利用する
・(2)確定申告ソフトを利用する
・(3)手書き
・(4)税理士に依頼する - 確定申告でトラブルや困りごとがあったら
・申告内容に誤りがあった場合
・期限内に申告ができなかった場合
・源泉徴収票の再発行
・税金の支払いが難しい場合 - Squareで確定申告作業の負担を軽減
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税」の額を計算し、納税する手続きのことです。原則として翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告書を提出します。
会社に勤めていて給与所得を得ている人であれば、すでに会社が給与から所得税分を差し引いて納税する源泉徴収が行われ、さらに年末に過不足分を計算し調整する年末調整が行われるため、基本的には確定申告の必要がありません。
一方で、個人事業主やフリーランスの人でも所得から源泉徴収されることはありますが、企業が完全に納税手続きを代行してくれるわけではありません。消費税の納付の有無やその金額、事業の経費、社会保険料の支払い状況の全体像は、事業主当人が把握しているため、所得と経費を整理、計算して自分自身で申告する必要があります。
所得や経費の計算に手間がかかることや、多額の税金を支払わなければいけないのではと心配する人もいるかもしれませんが、源泉徴収額などが過剰だった場合、つまり税金を納めすぎていた場合には、確定申告することで還付金を受け取れることもあります。
確定申告の基礎知識
この章では確定申告について押さえておきたい基礎知識をまとめています。以下が、この章で紹介する主な内容です。気になる箇所から読み進めてみてください。
- 確定申告関連で押さえておきたい単語
- 確定申告が必要な理由
- 確定申告の対象者
- 必要な書類や事前準備、申告期限
- 従業員がいる場合に必要な手続き
- 確定申告について相談できる場所
- 確定申告を税理士に依頼するといい場合
確定申告関連で押さえておきたい単語
確定申告にあまり慣れていないうちは、聞き慣れない単語に遭遇することもあるでしょう。ここでは確定申告をするにあたって、必ず目にする単語とその意味をまとめています。
| 💰 所得 | 給与所得や雑所得など、「所得」とは収入から経費や控除を差し引いた金額のことです。事業に必要な支出(消耗品・家賃・交際費など)が経費に含まれます。 |
| 🏢 源泉徴収 | 所得税を給与や報酬からあらかじめ差し引き、会社などが納税者に代わって納税する仕組みです。 |
| 📅 年末調整 | 従業員を雇っている場合に必要な手続きで、年末に源泉徴収額と本来の所得税額の差を精算します。 |
| 🟦 青色申告 | 確定申告の方法の1つで、詳細な帳簿付けが必要ですが、最大65万円の控除が受けられる節税効果の高い方法です。申請書を事前に税務署へ提出する必要があります。 |
| ⬜ 白色申告 | 確定申告のもう1つの方法が、白色申告です。手続きが簡単な代わりに特別控除はありません。青色申告を申請していない場合は自動的にこちらになります。 |
| 💡 控除 | 税負担を軽減する制度で、医療費控除や配偶者控除などさまざまな種類があります。自分が該当する控除を事前に確認しておきましょう。 |
確定申告が必要な理由
確定申告が必要な理由は大きく以下の2点です。
(1) 一定額以上の所得がある場合、所得税を納税しなければいけないため
(2) 正確な所得金額を申告し、所得税額を納付するため
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得金額と所得税額を計算して、税務署に申告・納付することです。会社員の場合は会社が当人に代わり「年末調整」という手続きを通して正確な所得金額と所得税額を算出するため、確定申告をしなくて済むことが一般的です(※)。
※年末調整では対応できない控除もあるため、こういった控除を受けたい場合は会社に勤めている場合も自分で確定申告することになります。
フリーランスや個人事業主の中には、源泉徴収や予定納税を通して所得税を納めている人もいるでしょう。源泉徴収や予定納税は決められた計算式(※)をもとに計算されているため、年間の所得金額をもとに再度計算すると過不足が出る可能性があります。
※100万円以下の報酬に対する源泉徴収税額は「報酬額 × 10.21%」、予定納税は「前年分の納税額の3分の2」
そのため、確定申告という手続きを通して正確な所得金額と所得税額を算出し、納めすぎた分は納税者に還付され、納め足りていない分は追加納税で帳尻を合わせます。
確定申告の対象者
会社員、個人事業主、フリーランス、アルバイトなど働き方を問わず、以下の条件1に当てはまると確定申告が必要です。
| 詳細 | |
| ☑️給与所得がある人 | (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた など |
| ☑️公的年金などの雑所得のみの方 | 公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある |
| ☑️退職所得がある方 | 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある |
| ☑️次の計算において残額がある方 | (1) 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。 (2) 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。 (3) 所得税額から、配当控除額を差し引きます。 |
上記の表を見て、「副業をしている場合はどこに当てはまるのか」と思う人もいるでしょう。副業をしている場合は、以下条件にあてはまると確定申告が必要です。
- 副業が雇用契約に基づくアルバイトなどで、所得が20万円を超える
- 副業が雇用契約に基づくアルバイト以外で、所得が20万円を超える
- 年収が2,000万円を超える
また、副業は種類によって、所得の区分が異なります。たとえば、アルバイトの収入は給与所得となり、クラウドソーシングでデザインの仕事をした場合には、どのような頻度で受注しているかなどによって事業所得または雑所得になります。事業所得にあたる場合には、青色申告ができ、特別控除や損益通算といった恩恵を受けられます。

必要な書類や事前準備、申告期限
2026年(令和7年分)の提出期限は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)です(e-Taxは1月5日2から受付開始予定)。消費税の申告は2026年3月31日(火)までです。この申告期限までに、確定申告書や本人確認書類、控除証明書などの必要書類を準備して税務署に提出します。
e-Taxを利用する場合には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを持っていない人向けの暫定的な措置として「ID・パスワード方式」も運用されていましたが、マイナンバーカードの普及に伴い、ID・パスワードの新規発行は2025年9月末で停止されました。2025年10月1日以降に新たにe-Taxを利用する人はマイナンバーカードでの申告になります3。
確定申告に必要な書類やe-Taxについては、こちらの記事も参考にしてください。
従業員がいる場合に必要な手続き
自営業やフリーランスの人の中には従業員を雇っている人もいます。このような場合は従業員の年末調整が必要です。
年末調整とは、所得税の過不足を精算する手続きで、10月下旬から11月頃に始めて、翌年の1月下旬までに終わらせるのが一般的です。事業者によって開始時期は異なりますが、多くの場合は11月下旬頃から関係書類を集め始めます。従業員の提出書類に漏れや記入ミスがないかどうかをチェックする必要があるため、スケジュールに余裕を持たせ、期日までに確実に必要書類を集めましょう。
確定申告について相談できる場所
確定申告についておおまかな概念は理解できても、確定申告書を作成するうえで不明点が出てくることもあります。確定申告の期間中には税務署内外で相談センターが設けられることがあります。ただ整理券が必要だったり混雑していたりすることが予想されるため、余裕を持って足を運ぶといいでしょう。
そのほかにも1年を通して、さまざまな団体や専門家がサポートを提供しています。わからない点があれば放置せず、早めに解決にあたると心に余裕を持って確定申告に挑めるでしょう。たとえば以下の場所では無料で相談を受け付けています。
- 管轄の税務署
- 国税庁の確定申告電話相談センター
- 市区町村役場の税務窓口
- 税理士会などによる街頭無料相談会
- 商工会議所
また、国税庁のチャットボット(ふたば)に相談することもできます。2025年分(令和7年分)の所得税や消費税については翌年1月あるいは2月から、相談を受け付ける予定となっています。
さらに、以下は有料ですがより細かなアドバイスをもらいたい場合にはぜひ検討してみてください。
- 青色申告会
- 税理士

確定申告を税理士に依頼するといい場合
自分の確定申告だからといって、すべてを自分で担う必要はありません。以下のような場合には、税理士に依頼することも検討してみましょう。
- 1年間の売り上げが1,000万円を超える人
- 税務処理にわずらわされずに本業に専念したい人
- 税務調査に備えたい人
一定以上の売り上げがある場合は、税理士費用をまかなえる可能性が高く、税理士に収入や経費の処理、確定申告を依頼し、業務効率を上げるのも一つの手です。また、顧問税理士がいることで、税務調査が入ったときなどにスムーズに対応できます。税務調査が心配だという人は税理士がいることで本業に専念できるでしょう。
課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税は免除されますが、前々年もしくは前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万を超える場合では消費税を納税する必要があります。消費税の処理までするのは重荷だという人も税理士への依頼を検討してみてください。
1年の終わりの12月になると、税理士事務所は年末調整などの業務で繁忙期に入ります。時間に余裕があれば、さまざまな税理士の中から自分と業務に合う人を選べるだけでなく、金額の交渉もしやすくなるため、繁忙期の前に余裕を持って依頼することをおすすめします。
税金に関する基礎知識や疑問を解決
ここからは税金にまつわる基礎知識を見ていきましょう。
個人事業主が納めるべき税金の種類
個人事業主が納めるべき税金は主に、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4種類です。
所得税は国が課す税金で、売り上げから経費や各種控除を差し引いた金額に対して課税されます。所得税額は確定申告時に申告・納付します。
消費税は課税売上高によるので、不安な場合は管轄の税務署や顧問税理士に問い合わせてください。住民税や個人事業税は前年の確定申告をもとに計算され、納税通知が届き、納付期限までに支払いを済ませる必要があります。
法人税とは
本記事は個人事業主やフリーランスの人を対象としていますが、中には将来的に事業を法人化したいという人もいるかもしれません。そのような人は法人税の基礎知識を押さえておくとよいでしょう。
法人税とは、法人が事業活動で得た所得にかかる税金のことです。個人事業主やフリーランスから法人成りをした人は、税務署に法人税の申告と納付をしなければなりません。法人税の納税額は、事業年度の所得金額に税率をかけて算出します4。
源泉所得税とは
源泉所得税とは、企業が従業員に毎月支払う給与(源泉)から所得税を差し引いて(徴収して)、国に納付する税金のことです。この仕組みのことを源泉徴収と呼びます。また、個人事業主やフリーランスに支払う報酬も源泉徴収の対象になることがあります5。
個人事業主やフリーランスの人は、自身の確定申告では、経費や控除金額を計算し、すでに源泉徴収されている所得税に過不足がないかどうかを計算し、申告します。また、従業員を雇って給与を支払っている場合には、従業員の源泉所得税を納付する必要があります。
インボイス制度による変更点
2023年10月1日からインボイス制度が開始しました。インボイス制度の開始に伴い、消費税の納付が免除されている免税事業者から、消費税を納付する義務のある課税事業者になる可能性があり、主に個人事業主や小規模事業者が該当します。
インボイス制度以降、仕入税額控除の適用を受けるには課税事業者のみ発行が可能な適格請求書(インボイス)が必要となります。免税事業者は、インボイスの交付ができないことを理由に取引先から取引条件を変更されるなど、事業継続に影響が出る可能性があります。このため、課税事業者への転向を検討しなければならない人もいるでしょう。課税事業者になると、消費税を納付することになり、消費税の計算や申告作業が発生します。
追徴課税とは
追徴課税は、実際よりも少なく税金を申告したり、無申告したりしたことが発覚した場合に課される税金です。場合によっては、数百万円から数千万円規模を支払わなければならないこともあります。追徴課税の支払いには納付期限の猶予がなく、原則的には一括で納付しなければならないため、事業の資金繰りは厳しくなります。事業者として追徴課税は避けたいところです。追徴課税のためだけでなく、社会の一員として確定申告と納税は必ず正しく行いましょう。

賢く上手に節税対策
ここではルールに従って、賢く、上手に節税する方法を紹介します。
控除制度を活用しよう
税金には「控除」という制度があり、条件を満たし正しく申告すると、所得や税額から一定の金額を差し引くことができます。
たとえば、医療費が一定額を超えると最大200万円までの控除を受けることができる、ということは耳にしたことがあるかもしれません。これは「医療費控除」に当てはまります。そのほかにも生命保険料を支払っている場合、ひとり親の場合、認定NPO法人に寄付をした場合など、実にさまざまな人が控除の対象となり得るので、当てはまるものがないか目を通しておくと節税が期待できます。
細かな説明をすると、控除には所得から差し引くことができる「所得控除」と、所得税額から差し引くことができる「税額控除」があります。どちらにも複数の種類の控除があり、以下の表ではこの2つを分けて紹介します。受けられそうな控除があるか、見てみましょう。
| 所得控除 | 税額控除 |
| ・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・寄附金控除 ・障害者控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・基礎控除 |
・配当控除 ・外国税額控除 ・認定NPO法人等寄附金特別控除 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 ・住宅耐震改修特別控除 ・中小事業者が機械などを取得した場合の所得税額の特別控除 ・給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除 など |
青色申告をしていると適用される税額控除もあるので、当てはまるものがないかどうかを国税庁のウェブサイトに公開されている「税額控除」のページで確認しておくといいでしょう。
家事按分を上手に活用
個人事業主やフリーランスの人の中には、自宅をオフィスとして利用していたり、パソコンやプリンターなど自宅にあるものを仕事上でも兼用していたりする人もいるはずです。プライベートとビジネスの区切りがつきにくいものについては「家事按分」を活用することで節税につなげられます。
家事按分の対象となるのは、家賃や水道光熱費、通信費、消耗品費など必要経費になるものです。経費の額は、業務として使用している面積の割合や時間の割合などから按分比率を算出し、経費となる金額を計算します。

ふるさと納税で税制メリットを享受
ふるさと納税は、地方自治体に対して寄付すると自己負担額の2,000円を除いた金額が控除される仕組みで、正確には節税対策ではありません。ただし、サポートしたい地方自治体を選んで、返礼品を受け取れるといったメリットを享受できます。
ふるさと納税については総務省のウェブサイトにわかりやすい説明があります。
確定申告のやり方4選
確定申告のやり方は複数あります。それぞれの方法を見比べてみましょう。
(1)確定申告書等作成コーナーを利用する
確定申告の電子申告(e-Tax)を希望する場合は、確定申告書等作成コーナーという国税庁のウェブサイトが利用できます。
e-Taxを選ぶと自宅から申告できるのはもちろんのこと、青色申告者は最大65万円の特別控除を受けられるので、書面で提出するよりもおすすめです。作成方法としては、画面の手順に従い、必要な箇所を記入していくかたちです。決算書や収支内訳書なども同サイトから作成します。途中まで記入して保存しておけるので、何回かに分けて記入を完了させていくこともできるでしょう。
(2)確定申告ソフトを利用する
確定申告ソフトは無料・有料とさまざまな種類があり、基本的には必要項目を入力していくことで申告用データを作成できます。
確定申告書等作成コーナーと流れは似ていますが、会計ソフトや家計簿ソフトと連携できるサービスを利用すると書類作成に必要な取引データをいっきに取り込めて、仕訳も自動で行われるなど、情報入力が一部自動化される機能も兼ね備えています。取引データが多い場合には、作業負担の軽減につながります。代表的な確定申告ソフトには「freee」や「マネーフォワード」などがあります。
(3)手書き
電子機器には弱い……という場合は、手書きで確定申告書類を提出することももちろん可能です。書類は税務署から手に入れるか、インターネットからダウンロードして印刷しましょう。インターネットから印刷する場合はサイズはA4、両面印刷は不可なので、気をつけましょう。

(4)税理士に依頼する
確定申告を税理士に代行してもらうのも一つの手でしょう。自分一人で行うとなるとわからない点が次々と出てきてしまうかもしれませんが、税理士に依頼してしまえば、間違える心配をせずに申告書の作成を委ねることができます。
正確な内容で提出できるほかにも、節税方法を教えてくれることもあります。報酬には数万円から数十万円ほどかかりますが、ある程度収益のあるビジネスを営んでいる場合には、依頼するメリットがあるかもしれません。
それぞれのメリット・デメリットを表で見比べてみましょう。
| メリット | デメリット | |
| ①確定申告書等作成コーナーを利用する | ①自宅から提出できる ②途中まで入力し保存しておける ③青色申告者は最大65万円の控除を受けられる |
①書類の作成に時間がかかる |
| ②確定申告ソフトを利用する | ①自宅から提出できる ②入力が一部自動化されることも ③e-Taxにも対応している |
①数千円の月額利用料がかかるのが一般的 ②サービスによって仕様が異なる |
| ③手書きで行う | ①パソコンが苦手な人でもできる | ①時間と手間がかかる |
| ④税理士に依頼する | ①正確な内容で提出できる ②節税のアドバイスももらえる |
①数万円から数十万円の費用を支払う必要がある |
確定申告でトラブルや困りごとがあったら
申告内容に誤りがあった場合
申告期限内に誤りに気づいたか、申告期限後に誤りに気づいたかで対応が異なります。申告期限内に誤りに気づいた場合は、再度申告書を提出できます。申告期限後に誤りに気づいた場合は、「更正の請求」または「修正申告」のいずれかを行わなければなりません。どちらに当てはまるかで手続きの方法は異なります。
また、収入の一部を申告していない場合には、「課税所得を減らす試み」とみなされ、加算税などのペナルティーが課される可能性もあります。申告の誤りに気づいたらすぐに手続きすることをおすすめします。

期限内に申告ができなかった場合
日々の業務に追われて期限までの提出が叶わなかった……ということもあるかもしれません。こういった場合はできるだけ早く申告するようにしましょう。なぜならこういった期限後申告には、基本的に所得税のほかに無申告加算税が課されるのが通常の流れだからです。しかし、期限からそこまで日数が経っていないうちに提出できれば、期限後申告でも無申告加算税を課されないこともあります。
期限後申告でも無申告加算税を課されないためには、以下の条件6を満たす必要があります。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
このように期限後申告でも無申告加算税を免れる方法はなくはないものの、できるだけ余裕を持って提出しようという姿勢が何よりも望ましいでしょう。
源泉徴収票の再発行
確定申告に必要な源泉徴収票を紛失してしまうこともあるかもしれません。源泉徴収票の再発行は、役所や税務署ではなく、会社の経理担当部署に連絡し、源泉徴収票を再発行してほしいと伝えることで、基本的には再発行してもらえます。
中には再発行を拒否された、会社が倒産しているなど、特殊なケースに当たる人もいるかもしれません。このようなケースも含め、源泉徴収票の再発行について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
税金の支払いが難しい場合
税金を期限内に納付できない場合、分割して支払う猶予制度があります。猶予を受けるには、申請書を管轄の税務署に提出し、税務署長から許可を受ける必要があります。詳しくは、国税庁のウェブサイトに案内が記載されています。
Squareで確定申告作業の負担を軽減
日々の業務の効率化をはじめ、確定申告作業の負担まで軽減できるサービスとして、Squareがあります。Squareは無料アカウントを作成するだけで、キャッシュレス決済をはじめとするさまざまな機能が無料もしくは低コストで利用できるサービスです。
Squareのサービスには以下のものがあります。
- 無制限に商品を登録できるSquare POSレジ
- ニーズに合わせて選べるキャッシュレス決済端末
- クラウド請求書の発行・送付ができるSquare 請求書
- ネットショップの開設・運営ができるSquare オンラインビジネス
- 数秒で商品購入ページが作成できるSquare リンク決済

上記の方法で受け付けたすべての決済は、管理画面からひと目で簡単に確認できます。期間を指定して売り上げを調べたり、必要なデータをダウンロードしたりすることもできるので、確定申告書類の作成には役立つでしょう。
なかでも特に便利なのは、確定申告ソフトも提供している「freee」や「マネーフォワード」との連携機能です。いずれかの会計ソフトと連携すれば、何もしなくても、Squareの売上データが自動で会計ソフトに取り込まれます。売上データを1つずつ打ち込まずに済むので業務量の削減に大きく貢献するでしょう。
詳しくは、「POSレジスタートガイド⑧ クラウド会計ソフトとの連携方法」の記事もご参考ください。
請求書の作成から送信まで簡単スピード対応
Square 請求書は決済機能付きのクラウド請求書サービスです。無料ではじめられ、自動送信や定期送信など便利な機能も盛りだくさん。フリーランス、個人事業主、業務請負やサービス請負業の請求業務を簡単に効率化できます。
確定申告は1年分の膨大な数字を相手にする手間のかかる作業ではありますが、事業の状態を把握するよい機会でもあります。また、普段からSquareや会計ソフトを利用することで、確定申告の負担を大きく減らせるだけでなく、制度変更や新制度にも対応しやすくなるので、こういった業務効率化ツールの導入も積極的に検討してみるといいでしょう。
確定申告が初めて、久しぶりという人は、確定申告を前に緊張するかもしれませんが、本記事を参考に、向こう数年を見すえたスムーズな確定申告の仕組みづくりに取り組んでみてください。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2022年12月26日時点の情報を参照しています。2025年11月24日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。