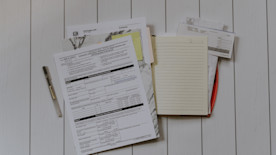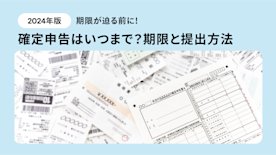白色申告とは?控除額や経費、必要書類と帳簿の付け方

青色申告以外で確定申告することを白色申告といいます。所得金額を正しく算出して納税するには、白色申告で受けられる控除や帳簿への理解が欠かせません。本記事では白色申告とは何か、控除額や経費に計上が可能なもの、必要な書類と帳簿の付け方などを解説します。
白色申告とは?
白色申告とは、青色申告以外で確定申告を行うことです。白色申告をしたことがない人は、いくらから申告が必要なのか気になるかもしれません。原則として、給与所得がない個人事業主は「年間の合計所得金額>所得控除」となった場合に確定申告が必要です。
白色申告と青色申告の違いを簡単にまとめると、簡易的な記帳が認められ経理業務の負担が比較的軽いのが白色申告です。青色申告は作成すべき帳簿や書類が多く、内容の厳密さが求められる代わりに税制優遇などの特典を受けられます。
青色申告を行うには開業届や事前の承認申請が必要です。白色申告では事前の承認申請は不要ですが、青色申告で受けられる税制優遇や特例が適用されない点には注意が必要です。たとえば青色申告では、適切な手続きを行うことで最高65万円の青色申告特別控除や純損失の繰越しおよび繰戻しなどを受けられます。
青色申告での優遇を受けるには白色申告では発生しない手間がかかるものの、税負担を軽減できる点はメリットです。業務負担の増加や会計知識に不安がある場合、税理士に業務を委託するという手段もあります。白色申告と青色申告のどちらを選ぶかは経理業務の負担だけではなく、事業の収益状況や税制優遇の効果など総合的な観点から判断しましょう。
白色申告での必要書類は以下の通りです。
・確定申告書
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
収支内訳書とは、取引の内容や金額を帳簿に記載したものです。記帳は必ずしも一つ一つの取引ごとに行う必要はなく、日々の合計金額をまとめて記載する簡易的な記帳も認められます。収支内訳書を作成する際は、国税庁が開示している手引きに沿って進めるとスムーズです。
各種控除は所得控除や税額控除などがあり、控除を受けるには各種証明書が必要です。紛失していると控除が受けられないため、手元にあるか確認しておきましょう。
確定申告の時期に入ってから記帳を始めたり必要書類をそろえたりすることは、業務負担の増加につながります。白色申告の具体的な必要書類や申告手順はあらかじめ確認し、日々の取引はその都度記帳しておくと安心です。
【参考ページ】
所得税等の確定申告とは|国税庁
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
所得税のしくみ|国税庁
No.2070 青色申告制度|国税庁
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)|国税庁
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告では、主に以下の点で違いがあります。
・確定申告における必要書類
・保存すべき帳簿と保存期間
・経理業務の負担
・税制優遇や特例の有無
まず、確定申告における両者の必要書類を整理しておきましょう。
白色申告
・確定申告書
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
青色申告
・確定申告書
・青色申告決算書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
両者で違うのは、「収支内訳書」と「青色申告決算書」です。収支内訳書は青色申告決算書よりも簡易的な書類です。青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書が含まれ、より詳細な記載が求められます。
次に帳簿類については白色申告、青色申告ともに日々の取引を記帳し、一定期間は帳簿類を保存する必要があります。以下は国税庁が開示している保存が必要な帳簿と書類の一例です。
白色申告
・収入金額、必要経費を記載した帳簿(7年)
・現金出納帳や売掛帳などの帳簿(5年)
・決算に関する棚卸表などの書類(5年)
・請求書、納品書、領収書など(5年)
青色申告
・仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛量、固定資産台帳など(7年)
・貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類(7年)
・領収書、預金通帳などの現預金取引関係書類(原則7年)
・請求書、見積書、契約書、納品書など(5年)
白色申告では日々の取引を一つ一つ記載するのではなく、合計金額をまとめて記載する方法が認められています。事業主の中には細かい記帳をしていない人もいるかもしれませんが、帳簿や書類の作成は正しい所得金額の申告につながります。会計ソフトなども活用しつつ作成してみましょう。
税制優遇や特例の有無については、青色申告のみに適用されるものが多くあります。例として以下の三つが挙げられます。
1. 最高65万円の青色申告控除
青色申告控除とは、所得金額から一定金額を控除するものです。所得金額が小さくなれば、税負担が軽減されます。控除額は最高65万円、次いで55万円ですが、一定の要件を満たす必要があります。65万円および55万円の控除要件のいずれも満たさない場合は10万円が控除されます。
2. 青色事業専従者給与の控除
青色事業専従者とは、青色申告を行う納税者と生計を一にする配偶者や親族で、納税者の事業に専念している人を指します。青色事業専従者給与の控除では、青色事業専従者に支払われた給与を必要経費に計上することが可能です。
3. 純損失の繰越しおよび繰戻し
事業で赤字があり損益通算をしても控除しきれない損失(純損失)がある場合は、翌年以降3年間にわたり損失額を各年の所得金額から控除することが可能です。所得金額が小さくなることで、税負担の軽減効果があります。
また、純損失の繰越しに代わり、損失額を前年に繰戻すことで前年分の所得税還付を受けることも可能です。ただし、この場合は前年も青色申告を行っている必要があります。白色申告では所得控除や専従者給与控除などが受けられることがあります。両者の違いを理解し、選択した申告方法に沿った準備を進めましょう。
【参考ページ】
No.2070 青色申告制度|国税庁
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、経理の業務負担が青色申告よりも軽いことです。白色申告で必要となる収支内訳書は比較的簡易的なものであることから、基礎的な会計や経理の知識で対応できます。帳簿を作成したことがなくどうすれば良いのか分からない場合は、国税庁が開示している手引きを参考に進めるとスムーズです。
業務負担の観点では白色申告が優位ですが、青色申告よりも特典が少ない点には注意が必要です。最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除、青色事業専従者給与の控除や純損失の繰越しおよび繰戻しは青色申告者のみに適用されます。
白色申告と青色申告のどちらにすべきか判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。今すぐ青色申告者となることは難しくても、事業規模の拡大により切り替えることも想定しておくことで、確定申告の準備もスムーズに進むでしょう。
【参考ページ】
「帳簿の記帳のしかた」(PDF)|国税庁
白色申告の控除額
白色申告で受けられる所得控除について整理しましょう。
1. 社会保険料控除
配偶者や親族の社会保険料を納税者が負担した場合、その金額は社会保険料控除の対象です。その年に支払った金額または給与などから差し引かれた金額は全て控除できます。
社会保険料控除には、健康保険、国民年金、厚生年金保険、国民健康保険などの保険料が該当します。
控除を受けるには、保険料または掛金額を白色申告の際に提示します。
2. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済などの掛金は全額が控除の対象です。小規模企業共済の月額掛金は最高7万円(年間84万円)です。1年以内の前納掛金も控除対象となるため、該当する場合は控除を忘れないようにしましょう。
3. 生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料や個人年金保険料を支払った場合は、年間の支払保険料等に応じて一定額の控除が可能です。控除額は生命保険を契約した年月日により異なります。
・平成24年1月1日以後に締結
年間の支払保険料などが8万円以上であれば4万円の控除
・平成23年12月31日以前に締結
年間の支払保険料などが10万円以上であれば5万円の控除
控除を受けるには確定申告書への記入と、支払金額や控除を受けられることを証明する書類などの提示が必要です。
4. 地震保険料控除
損害保険契約などで地震などの損害部分に対して保険料や掛金を支払った場合は、一定金額の控除が受けられます。
・年間の支払保険料が5万円以下
支払金額の全額を控除
・年間の支払保険料が5万円超
5万円の控除
控除を受けるには確定申告書に記載し、支払金額や控除が受けられることを証明する書類などの提示が必要です。
5. 寡婦控除
納税者が寡婦の場合、令和2年分以後は一律27万円の控除が受けられます。令和2年分以後で寡婦に該当するのは、ひとり親に該当せず以下のいずれかに当てはまる人です。
・夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族がおり合計所得金額が500万円以下
・夫と死別後に婚姻していないもしくは夫の生死が不明で、合計所得が500万円以下
寡婦控除を受ける場合は確定申告書の第二表でチェック事項があるので、忘れないようにしましょう。
6. ひとり親控除
納税者がひとり親である場合、一律35万円の控除を受けられます。ひとり親とは、婚姻していないまたは配偶者の生死が不明で以下の全てに当てはまる人です。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
・生計を一にする子がいる
・合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除も確定申告書の第二表にチェック事項があります。
7. 勤労学生控除
納税者が勤労学生である場合、一律27万円の控除を受けられます。勤労学生とは、たとえば働いて所得を得ており、特定の学校の学生である人です。
控除を受けるには、給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載し勤務先に提出します。確定申告をする場合は、確定申告書にある勤労学生控除に関する事項へ記載が必要です。
8. 障害者控除
納税者自身、生計を一にする配偶者または扶養親族が障害者である場合、区分に応じて一定額の控除を受けられます。
・障害者
27万円
・特別障害者
40万円
・同居特別障害者
75万円
9. 配偶者控除
控除対象となる配偶者がいる場合、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じて一定額の控除が受けられます。
たとえば納税者本人の合計所得金額が900万円以下である場合、38万円の配偶者控除が受けられます。この場合、控除対象配偶者が70歳以上であれば、48万円の控除が可能です。
控除対象となる配偶者は、以下の四つの要件の全てに該当する人です。
・民法規定による配偶者(内縁関係は該当しない)
・生計を一にする配偶者
・年間の合計所得金額が48万円以下(所得が給与のみであれば103万円以下)
・その年に一度も青色事業専従者として給与を受けていない、または白色事業専従者でない
配偶者控除を受けるには、確定申告書に控除額と配偶者の氏名やマイナンバーなどを記入します。
10. 配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円超であり配偶者控除の対象外であっても、配偶者控除の合計所得金額に応じて一定額の控除を受けられます。納税者本人の合計所得金額が900万円以下かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下であれば、控除額は38万円です。配偶者の合計所得金額が133万円を超えると控除はありません。配偶者特別控除を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件の一つです。
11. 扶養控除
納税者に控除対象扶養親族がいる場合は、一定額の控除が受けられます。扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族や里子などで、年間の合計所得金額が48万円以下である人です。したがいまして、所得が給与のみであれば年収103万円以下までが対象です。
控除額は以下の四つに区分されます。
・一般の控除対象扶養親族
38万円
扶養親族のうち、12月31日時点で16歳以上であれば控除対象親族に該当します。
・特定扶養親族
63万円
控除対象親族のうち、12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば特定扶養親族に該当します。
・70歳以上かつ同居していない老人扶養親族
48万円
・70歳以上かつ同居している老人扶養親族
58万円
控除を受けるには、確定申告書に控除額と扶養親族の氏名やマイナンバーなどを記入します。
12. 基礎控除
基礎控除の控除額は、合計所得金額が2,400万円以下であれば一律48万円です。2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円の控除を受けられます。合計所得金額が2,500万円を超えると控除はありません。
13. 雑損控除
雑損控除とは、災害、盗難や横領によって資産の損害を受けた場合に一定額を控除できるものです。資産は納税者本人もしくは総所得金額が48万円以下の配偶者やその他親族が所有するものに限られます。また、対象資産はあくまでも生活に必要なものに限定され、別荘など趣味・娯楽に関する資産は対象外です。
控除額は以下で算出された金額のいずれか多い金額です。
・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金などの額)-(総所得金額など)×10%
・(災害関連支出の金額-保険金などの額)-5万円
控除を受けるには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害などで支出した金額の領収証などを提示する必要があります。
14. 医療費控除
1月1日から12月31日の間に、自分や自分と生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられます。控除額は最高200万円で、原則として以下の計算式で算出されます。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。医療費通知を交付されていれば、明細書の記載を簡略化できます。
15. 寄附金控除
国や地方公共団体などに特定寄附金を支出した場合、寄附金控除の対象です。寄附金控除額は、以下のいずれか低い金額から2,000円を差し引いた金額です。
・支出した特定寄附金の合計額
・総所得金額などの40%相当額
控除を受けるためには、確定申告に寄附金控除に関する事項を記載し、寄附した先から交付された受領書などを提示します。
白色申告では、所得控除に加えて事業専従者控除があります。控除額は以下のいずれか低い金額です。
・配偶者は86万円、配偶者以外は一人50万円
・控除前事業所得などの金額を「専従者+1」の数で割った金額
事業専従者に該当するのは、その年の12月31日時点で15歳以上であり、白色申告者の事業に専念している人です。控除を受けるには確定申告に控除額を記載します。
白色申告者が受けられる各種控除の金額はその人の状況により異なります。どの控除が対象なのか整理し、証明書などがそろっているか確認しましょう。
【参考ページ】
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
No.1130 社会保険料控除|国税庁
No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁
No.1140 生命保険料控除|国税庁
No.1145 地震保険料控除|国税庁
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
No.1160 障害者控除|国税庁
No.1170 寡婦控除|国税庁
No.1171 ひとり親控除|国税庁
No.1175 勤労学生控除|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
No.1180 扶養控除|国税庁
No.1199 基礎控除|国税庁
白色申告で経費にできるものと上限額
白色申告で経費にできるものは、事業を行うために必要と認められるものに限られます。経費に上限額はありませんが、適切な勘定科目で内容を明瞭に記帳することが重要です。ここでは、経費計上の際に使用する主な勘定科目とその内容を整理します。
・租税公課
租税公課に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・固定資産税、不動産取得税、事業税、自動車取得税
・農業協同組合や商工会議所などの賦課金
所得税、住民税、延滞税などは含まれません。
・水道光熱費
水道光熱費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・水道代、電気代、ガス代
・灯油の購入費
・旅費交通費
旅費交通費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・電車、バスの運賃
・宿泊代
・通信費
通信費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・事業のために利用した電話料
・インターネット料金
・広告宣伝費
広告宣伝費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・新聞、雑誌、テレビなどの広告費用
・広告名入りのカレンダー
・接待交際費
接待交際費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・取引先に出す飲食代
・会議に出す飲食物の購入費用
接待交際費は事業に使用したものと私用での支出が混同しやすい費用です。経費へ計上する際には、取引先の名称や人数、飲食があった年月日、飲食などに利用した店の名称および所在地などを記録しておきましょう。
・損害保険料
損害保険料に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・火災保険料
・自動車の損害保険料
・修繕費
機械や店舗などの修理代は修繕費に計上できます。修繕費の計上では、資本的支出と間違えないように注意が必要です。改良などにより固定資産の価値や耐久性が高まるといった場合は、修繕費ではなく減価償却の方法を用いて経費処理します。
・消耗品費
消耗品費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・帳簿、文房具、用紙などの購入費
・使用可能期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
・減価償却費
建物や機械装置など、時の経過により価値が減っていく資産は減価償却資産の対象です。これらは取得した年に全額費用計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたって分割して必要経費に計上します。
・福利厚生費
福利厚生費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・従業員の慰安のための費用
・医療や保健などのために事業主が支出した費用
・事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金の保険料や掛金
・給与賃金
給与賃金に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・給料、賃金、退職金
・食費、被服などの現物給与
・利子割引料
事業用に借入をした際の利子や受取手形の割引料などは利子割引料に含まれます。
・地代家賃
地代家賃に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・店舗、工場、倉庫などの敷地の地代
・賃借している工場や倉庫などの家賃
・外注工賃
修理加工などで外部注文した場合の加工賃などが含まれます。
【参考ページ】
No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁
確定申告書等作成コーナー やさしい必要経費の知識|国税庁
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
租税公課|国税庁
確定申告書等作成コーナー 租税公課|国税庁
確定申告書等作成コーナー 水道光熱費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 旅費交通費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 通信費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 広告宣伝費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 接待交際費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 損害保険料|国税庁
確定申告書等作成コーナー 修繕費|国税庁
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁
No.5402 修繕費とならないものの判定|国税庁
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却|国税庁
確定申告書等作成コーナー 消耗品費|国税庁
No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
確定申告書等作成コーナー 福利厚生費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 給与賃金|国税庁
確定申告書等作成コーナー 利子割引料|国税庁
確定申告書等作成コーナー 地代家賃|国税庁
確定申告書等作成コーナー 専従者給与と専従者控除とは|国税庁
白色申告のやり方
白色申告のやり方は大まかに以下のステップの通りです。
1. 各種帳簿や書類の作成
2. 決算に向けた帳簿の整理
3. 確定申告書と収支内訳書の作成
4. 各種控除に必要な添付書類の準備
5. 提出
6. 納税
また、申告書の提出方法は以下の三つがあります。
1. e-Tax
2. 郵便または信書便で税務署へ送付
3. 税務署の受付へ提出
白色申告の期限はあらかじめ決められているため、申告方法を含め事前にやるべきことを把握しておきましょう。令和5年分の確定申告の期間は、令和6年2月16日~3月15日でした。例年この時期が申告期間となるので、白色申告について不明点がある場合は税理士や税務署などへ早めの相談が重要です。
実際に白色申告の手続きを始める前に、必要な帳簿の作成と整理が必要です。まずは棚卸資産を確認し、棚卸表を作成しましょう。商品の種別ごとに品名、数量、単価と合計金額を明らかにします。棚卸表を作成したら、その年の1月から12月までの取引を記帳した帳簿内容に間違いがないか確認をします。請求書や納品書などを参考にし、誤りがあれば訂正します。
次に、決算に向けて帳簿の整理を行います。ここでは前受金、前払費用、未収入金などに注意が必要です。その年の収入金額や必要経費になるものかどうかを確認し、整理しましょう。
収入金額と必要経費について整理できたら、次は減価償却費の計算を行います。建物や機械装置などを取得するための費用はその年に一括で費用計上するわけではありません。資産別に定められた耐用年数を基にして計算し、その年の期間に対応する減価償却費のみを必要経費に計上します。
減価償却費の計算以外にも、固定資産の損失、債権の貸倒れがあればこちらも金額を整理します。これらの作業が終了したら、白色申告で必要となる確定申告書と収支内訳書の作成に取り掛かりましょう。これらの書類は国税庁のホームページからダウンロードして記入が可能ですが、e-Taxを利用すればスマートフォンやパソコン上で白色申告が完了します。
e-Taxで白色申告を行うのであれば、事前にマイナンバーカードの発行、受付システムへの登録や利用者識別番号の取得などが必要です。一日で手続きが終わらない可能性もあるため、確定申告の時期が来る前に準備することをおすすめします。
白色申告は提出して終わりではなく、納税まで済ませる必要があります。納税方法は振替納税、ATM、クレジットカードなどキャッシュレス決済が可能です。住民税については、5月〜6月に送付される決定通知書にある金額を払いましょう。
【参考ページ】
令和4年分白色申告者の決算の手引き(PDF)|国税庁
令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)|国税庁
申告書の提出方法|国税庁
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
白色申告の必要書類と書き方
まずは、白色申告の必要書類を改めて整理しましょう。
・確定申告書
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
確定申告書と収支内訳書は国税庁のホームページからダウンロードするか、e-Taxを利用してスマートフォンやパソコンの画面上からそのまま入力します。自分が決めた申告方法に応じて作成を進めましょう。
確定申告書のうち、第1表と第2表の主な項目はそれぞれ次の通りです。
1. 第一表
・収入金額等
・所得金額等
・各種所得控除額
・税金の計算
・その他
「税金の計算」では、配当控除、住宅借入金等特別控除や源泉徴収税額などを記入し、納税額あるいは還付税額を算出します。「その他」では配偶者の合計所得金額、専従者給与控除額(白色申告)や青色申告特別控除額(青色申告)を記入します。
2. 第二表
・所得の内訳
・総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
・配偶者や親族に関する事項
・小規模企業共済掛金控除/社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
・雑損控除
・寄附金控除
・事業専従者に関する事項
・住民税、事業税に関する事項
確定申告書の作成にあたり、手元には収入金額、所得金額、各種控除額が分かる帳簿や書類を用意しておきましょう。
白色申告で必要な収支内訳書は、控えを除いて2ページで構成されます。主な記入項目は以下の通りです。
1. 1ページ目
・収入金額
・売上原価
・経費
・専従者控除
・給与賃金の内訳
・税理士、弁護士等の報酬・料金の内訳
・事業者専従者の氏名等
「収入金額」では売上金額の他に家事消費の金額も記入します。家事消費とは、商品などを家事のために消費する、あるいは贈与することです。「売上原価」では期首と期末の棚卸高を記入します。また、その年の仕入金額も記入しますが、買掛で仕入れて代金はまだ支払っていないものも含まれます。「経費」は勘定科目を確認して計上し、領収書なども適切に保存しておきましょう。
2. 2ページ目
・売上(収入)金額の明細
・仕入金額の明細
・減価償却費の計算
・地代家賃の内訳
・利子割引料の内訳
「売上(収入)金額の明細」および「仕入金額の明細」では、取引先名、所在地、売上(収入)や仕入金額を記入します。取引金額順に整理しておくと記入がスムーズです。「減価償却費の計算」では、取得価額や耐用年数などを基に、その年の償却期間に応じた減価償却費を算出します。正確に算出するために取得年月や耐用年数を確認しておきましょう。
本人確認書類については、マイナンバーカードがあればその写しを添付します。マイナンバーカード未発行の場合、通知カードもしくは住民票の写しのいずれかと、運転免許証や公的医療保険の被保険者証などが必要です。
所得控除は必要な証明書を添付できなければ控除を受けられないものがあります。もし証明書を紛失した場合は、再発行が可能かどうか確認が必要です。
【参考ページ】
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)|国税庁
令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)|国税庁
白色申告に必要な帳簿と付け方
白色申告の帳簿および書類について、国税庁は以下の作成や保存が必要であると示しています。
・収入(売り上げやその他収入)金額、仕入金額、必要経費額が分かる帳簿
・現金の動きや残高を記載した現金出納帳、売掛帳などの帳簿
・棚卸表などの書類
・請求書や領収書など
具体的な記帳の内容は、以下の通りです。
1. 売り上げおよび仕入れ
・取引の年月日
・取引先の名称
・金額
2. 雑収入等
・取引の年月日
・雑収入等の内容、取引先の名称
・金額
3. 経費
・取引の年月日
・経費の内容、支払先の名称
・金額
経費は内容により給与賃金、外注工賃、減価償却費などに区分し、それぞれについて上記の内容を記帳します。
事業所得などがある白色申告者は、売り上げ、仕入れ、経費については一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載することも可能です。簡易的な方法による記帳として、たとえば以下が挙げられます。
・ 売り上げ
・小売、飲食店などの現金売り上げは、日々の合計金額のみをまとめて記載可能
(小売や飲食店以外の業種であっても、現金売り上げが少額であれば同様の記載が可能)
・保存している納品書控、請求書控などで取引内容を確認できるものは、日々の合計金額のみをまとめて記載可能
特に小売や飲食店では、不特定多数の顧客と日々多くの取引があると考えられます。それらを個別に記帳することは経理業務の負担増加につながるため、簡易的な方法による記帳が便利でしょう。
・ 仕入れ
・少額の現金仕入れは、日々の合計金額のみをまとめて記載可能
・保存している納品書控、請求書控などで取引内容を確認できるものは、日々の合計金額のみをまとめて記載可能
仕入れにおいても売り上げと同様の対応が認められます。
・ 経費
・少額な費用は、費用項目ごとに日々の合計金額のみをまとめて記載可能
経費は何に使われたのか明確にするために、科目を正確に区分して記帳しましょう。領収書などがない場合は経費と認められない可能性もあるため、紛失しないよう管理することが求められます。
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。仕入税額控除には、原則として一定の事項を記載した帳簿および適格請求書などの保存が求められます。経過措置はあるものの、自分にあった対応方法を早めに検討しておきましょう。
令和5年分の確定申告書より、税務調査で売り上げに関する帳簿の保存や記載が不十分であると判明した場合、加算税が上乗せされる可能性があります。帳簿をつけていない場合、まずは手書きでノートにメモをしてみるといった方法から始めることも大切です。
国税庁のホームページでは、練習用に帳簿のテンプレートをダウンロード可能です。記載例も参考にしつつ、効率を求めるのであれば会計ソフトの利用も検討してみましょう。
【参考ページ】
記帳説明会のご案内|国税庁
記帳の仕方がわからない方へ|国税庁
記帳のしかた(PDF)|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
記帳のしかた 白色申告編(PDF)|国税庁
白色申告に関するよくある質問
白色申告とは、青色申告以外で確定申告を行うことです。白色申告は青色申告決算書と比較すると帳簿類の作成も簡易的であり、会計の知識があまりない事業主でも対応しやすいのが特徴です。
白色申告では所得控除などが受けられますが、青色申告にある税制優遇や特例はありません。経理の負担の大きさだけではなく控除額も確認し、どちらで確定申告するか決めましょう。
白色申告では確定申告書、収支内訳書と所得控除に必要な各種証明書などを用意します。正しく所得金額を申告するため、収入金額や必要経費などを日々記帳することが重要です。
白色申告と青色申告では、以下について違いがあります。
・確定申告における必要書類
・保存すべき帳簿と保存期間
・経理業務の負担
・税制優遇や特例の有無確定申告書において、白色申告では収支内訳書、青色申告では青色申告決算書を提出します。青色申告決算書では貸借対照表と損益計算書の作成が必要であり、より厳密さが求められます。
これらの必要書類は日々記帳した帳簿や書類を基に作成します。白色申告では収入金額、必要経費や売掛金などが分かるように記帳しましょう。
優遇や特例について、青色申告では最高65万円の青色申告特別控除などが認められます。白色申告ではこのような優遇はなく、所得控除や事業専従者控除などに限られる点には注意しましょう。
白色申告は、以下のような人に向いています。
・経理業務の初心者
・経理業務の負担を抑えたい白色申告は経理業務の初心者に向いています。青色申告では勘定科目への理解と厳密な記帳が必要であり、帳簿類の作成難易度が上がる可能性があります。白色申告の収支内訳書は青色申告よりも記載内容も少なく、経理業務の初心者でも対応しやすいでしょう。
将来的な青色申告も視野に入れつつ、まずは基本的な記帳や確定申告の手順に慣れることが重要です。
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。