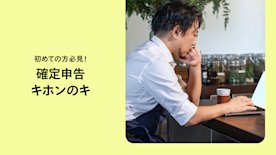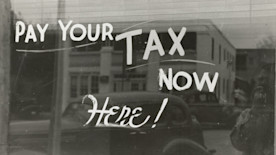税金とは?税収の仕組みと使い道、税金の種類と計算方法

起業したものの、税金についてあまり詳しくないという人もいるのではないでしょうか。本記事では税収の仕組みと使い道、税金の種類など基礎的な内容の解説や、個人事業主向けに簡単なシミュレーションなどを紹介します。事業などで利益が出れば税金を納める必要がありますが、まずは税金とはどのようなものなのか概要を理解しておきましょう。
税金とは?
税金とは、社会を支えるために国民が出し合うお金です。私たちが聞き慣れた税金といえば、消費税、所得税、法人税などが挙げられます。生活や事業を営む上で納税は国民の三大義務の一つですが、そもそもなぜ必要なのか立ち止まって考えたことはない人もいるかもしれません。
私たちが納めた税金は、インフラ整備や公共サービスの維持などに使われます。仮に税金がなければ、現在はお金がかからないサービスが有料になるかもしれません。したがって、国民一人一人が適切に納税することは、結果として私たちが暮らしやすい社会を築くことにもつながります。
税金にはさまざまな種類があり、正確な金額を納税する義務があります。もし申告内容に誤りがある、故意に過少申告するといったことがあれば、修正やペナルティを受けなければなりません。まずは税金の概要を理解し、分からない点は税理士へ相談をして解決することをおすすめします。
【参考ページ】
税のしくみ-税の種類と分類 | 税の学習コーナー|国税庁
税収の仕組みと使い道
税金が何に使われるのか、実は細かくは知らない人もいるかもしれません。財務省が発表している「令和5年度予算政府案」では税収(歳入)と使い道が示されています。
まず、主な税収の内訳については以下の通りです。
・所得税
・法人税
・消費税
・建設公債
・特例公債
税収の過半数は所得税、法人税や消費税などが占めています。このことからも、たとえば事業で発生した所得にかかる税金を適切に申告することは、社会を支えることにもつながることが分かります。建設公債とは、道路やダム建設などを行うために発行される債券です。建設公債を発行しても不足があると見込まれる場合には特例公債が発行されます。
次に、集まった税金の使い道(歳出)は以下の通りです。
・社会保障
・防衛関係
・公共事業
・文教および科学振興
・新型コロナ、原油価格、物価高騰対策
・地方交付税交付金
・債務償還債
・利払費
社会保障費は税金の使い道の中でも最も大きな割合を占めています。具体的には、年金、医療や介護に関連した費用です。税金が使われているおかけで年金の受け取りや医療費の一部負担などが実現しています。公共事業は新技術を活用した老朽化対策、水害対策など、防災・減災などに使われる費用です。また、地域の交通インフラの構築も公共事業費に含まれます。このほか、日本を取り巻く環境に合わせ、国として強化すべきポイントに税金が使われています。
【参考ページ】
財務省 令和5年度予算政府案
財務省 令和5年度の予算のポイント(PDF)
財務省 赤字国債と建設国債の違いを教えてください
公債 | NHK for School
財務省 社会保障(参考資料)
日本の税収の推移
税金について簡単に整理したところで、日本の税収の推移を見てみましょう。財務省が公表している「一般会計税収の推移」では、2009年から税収は右肩上がりです。2019年は一度減収したものの、その後は増収で2021年、2022年、2023年と3年連続で過去最高を更新しています。
2020年にコロナ禍でも税収が増えたのは、政府が景気対策などに乗り出したことが要因の一つと考えられます。その後も人々の動きに活気が戻り経済が正常化した結果、多くの商品やサービスが消費されたことが消費税の増収につながりました。また、円安が進行したことで業績が好調であった企業もあり、法人税や所得税の増収要因となりました。
税収が増えていることは経済が堅調に推移しているとも考えられますが、安心できる点ばかりではありません。少子高齢化による社会保障費の増加や、地政学リスクの高まりによる防衛費増加にも税金は必要です。今後、一部の税金で税率の引き上げが実施される可能性もあるため、税収とその使い道については意識しておくと良いかもしれません。
【参考ページ】
税収に関する資料 : 財務省
“コロナ危機なのに税収増の謎”を答え合わせ ~まさかの税収増をもたらした4つの要素~ | 星野 卓也 | 第一生命経済研究所
税収増が止まらない ~2022年度は72兆円程度への上振れを予想~ | 星野 卓也 | 第一生命経済研究所
「なぜ?税収は過去最高でも借金増」|サクサク経済Q&A|NHK
税金の納付時期
納税手続きが必要な主な税金として、以下が挙げられます。
・申告所得税、復興特別所得税
・法人税
・消費税、地方消費税
・贈与税
・相続税 など
上記について、いつ支払うのか、支払わなければどうなるのかなどを確認しておきましょう。
1. 申告所得税、復興特別所得税
2024年分の確定申告と納付期限は、2025年3月17日(月)です。申告書の受付は2025年2月17日(月)から開始(電子申告の場合は2025年1月上旬)されるので、早めに申告の手続きを行いましょう。
その年の5月15日時点で、前年の所得金額などを基に納税金額を計算して15万円以上になる場合は予定納税が可能です。予定納税は通常の確定申告の時期よりも申告期限が早いため、国税庁のホームページで確認しておくと安心です。
確定申告の内容が間違っており過少申告した場合は、修正申告が必要です。自分で気付かずそのままにしていた場合、税務署などから通知が来る可能性があります。その場合、不足分の税金だけではなく過少申告加算税や重加算税がかかってしまうかもしれません。
また、修正申告する場合は、本来の確定申告の申告期限の翌日から修正申告で納付する日までの期間にかかる延滞税が発生する場合があります。まずは確定申告を正しく行うように注意し、仮に修正が必要な場合は速やかに手続きを進めましょう。
納税額を多く申告してしまっていた場合は、更正の請求が可能です。請求内容が認められれば多く納税してしまった分が還付されます。ただし、こちらも期限が決められているため国税庁のホームページで確認しておくことをおすすめします。
2. 法人税
法人税の納付期限は、事業年度終了の翌日から2ヵ月以内です。たとえば事業年度が3月31日で終了する場合、5月31日までに納付しなければなりません。個人の確定申告と同じく、申告内容に誤りがあった場合は修正申告や更正の請求ができます。
3. 消費税、地方消費税
消費税および地方消費税の申告と納税期日は個人事業主と法人で異なります。2024年分の個人事業主の消費税の確定申告書の提出期限は、2025年4月1日です。毎年大きく時期は変わらないものの、曜日の関係で毎年全く同じとは限らないため、国税庁のホームページで確認しておきましょう。法人は事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告と納税をします。
4. 贈与税
贈与税が発生する場合、2024年分の申告と納付期限は2025年3月17日です。毎年必ず同じ日付とは限らないため、こちらも国税庁のホームページで確認が必要です。
5. 相続税
相続税の申告と納付期限は、相続の開始があることを知った日の翌日から10日以内です。相続については専門性の高い分野であるため、税理士などのサポートも検討してみましょう。税金により申告や納付期限が違うため注意が必要です。また、申告期限に誤りがあった場合の手続きについても一度整理しておきましょう。
【参考ページ】
申告と納税|国税庁
No.2040 予定納税|国税庁
国に治める国税の種類
国税と地方税は大きく分けて所得課税、資産課税、消費課税の三つに分類されます。具体的な国税の種類の一例を以下に挙げます。
1. 所得課税
・所得税
・法人税
・地方法人税
所得税は個人の所得にかかるものであり、法人税は法人にかかるものです。所得税は課税所得金額に応じて5%〜45%まで7つの区分があります。また、適用される税率に応じて控除があり、たとえば税率10%の場合の控除額は9万7,500円です。
普通法人における法人税は、まず資本金が1億円以下かどうかで区分されます。資本金が1億円以下であれば、課税所得が800万円以下の部分と800万円を超える部分でそれぞれ別の税率が適用されます。
・800万円以下の部分の税率 15%(適用除外事業者は19%)
・800万円を超える部分の税率 23.20%
地方法人税は、法人税額の10.3%を納める税金です。
2. 資産課税等
・相続税、贈与税
・登録免許税
・印紙税
個人が財産を相続した場合は相続税が発生します。贈与税については法人も納税義務があります。個人と法人間の贈与は財務処理も複雑であるため、専門家へ相談することをおすすめします。
登録免許税は不動産の登記や、個人あるいは会社が商業登記する際に課される税です。たとえば売買による土地の所有権の移転登記であれば、税率は不動産価額の1000分の20です(2026年3月31日までの登記には軽減税率あり)。また、株式会社の設立にかかる登記での税率は資本金額の1,000分の7です。
印紙税とは、収入印紙という契約書などに貼る小さな切手のようなものをもって納税とみなすものです。金額は作成する文書の種類や契約金額により異なります。
3. 消費課税
・消費税
・酒税
・たばこ税 など
生活にも密接な消費税は、個人事業主にとっても処理が重要な税金です。税金に関する制度の中でもインボイス制度の開始は事前の検討と準備が必要となるため、内容を理解しておきましょう。
酒税は酒税改正に注意が必要です。2023年10月に醸造酒類の税率は1klあたり10万円に一本化されます。お酒の区分に応じて税率は異なるため、気になる人は国税庁のホームページで確認してみることをおすすめします。
たばこ税は数ある税金の中でも税率が重いものの一つです。税額はたばこ一箱(20本入り/580円)に換算すると約360円であり、低下の約6割を占めます。
【参考ページ】
税の種類に関する資料 : 財務省
No.2260 所得税の税率|国税庁
No.5759 法人税の税率|国税庁
総務省|地方税制度|地方法人税(国税)
No.4152 相続税の計算|国税庁
No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
酒税に関する資料 : 財務省
たばこ税 | たばこ関連情報 | (一社)日本たばこ協会
都道府県に治める地方税の種類
代表的な道府県税として、以下が挙げられます。
・道府県民税
・事業税
・地方消費税
・自動車税
・不動産取得税
住民税は所得割と均等割から構成されます。
所得割:10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
均等割:5,000円で(道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)
事業者であれば、地方消費税の納税義務者となる場合があります。個人でも消費税の納税義務がありますが、法人では地方消費税という名目で同様に納税しなければなりません。
自動車税は総排気量および営業用か自家用かによって税額が異なります。詳細は国土交通省のホームページで確認が可能です。
【参考ページ】
税の種類に関する資料 : 財務省
総務省|地方税制度|地方税体系
総務省|地方税制度|地方消費税
国土交通省 自動車税
総務省|地方税制度|不動産取得税
市区町村に治める地方税の種類
代表的な市町村民税として、以下が挙げられます。
・市町村民税
・固定資産税
・軽自動車税
固定資産税は、税額を計算する際のベースとなる資産の金額(課税標準額)に対して1.4%の税率です。どのような固定資産であるかにより具体的な計算方法は異なります。正確な税額を算出するには、専門家の知識を借りることも有効です。軽自動車税は自家用であれば1万800円です。
【参考ページ】
税の種類に関する資料 : 財務省
総務省|地方税制度|個人住民税
総務省|地方税制度|地方税体系
総務省|地方税制度|固定資産税
総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割
個人事業主が支払う税金の計算方法・シミュレーション
ここで、以下の条件の個人事業主にかかる税額を簡単にシミュレーションしてみます。
年収:2,000万円
必要経費:300万円
所得控除:150万円
所得控除額は申告納税者の収入や家庭状況などにより異なります。国税庁が公表している「標本調査結果(令和3年分調査)」では、申告納税者の平均所得控除額は145万5,000円とあります。この金額を参考にし、このシミュレーションでは所得控除額を150万円に設定します。
まずは、課税所得を計算しましょう。
2,000万円ー300万円=1,700万円(所得金額)
1,700万円ー150万円=1,550万円(課税所得金額)
次に、所得税を求めます。所得税の税率は5%〜45%まで7つの区分があり、控除額は税率が高くなるほど大きくなります。詳細は国税庁のホームページから確認が可能です。
今回は課税所得額が1,550万円なので、税率は33%、控除額は153万6,000円です。
1,550万円×33%ー153万6,000円=357万9,000円
以上より、所得税額は357万9,000円という結果になりました。
【参考ページ】
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 標本調査結果(令和3年分調査)調査結果の概要
法人が支払う税金の計算方法・シミュレーション
次に、法人税額の簡単なシミュレーションをしてみましょう。実際の課税所得の算出は益金算入・益金不算入、損金算入・損金不算入などの計算もあり、やや複雑です。ここではシンプルに「利益=課税所得」として計算します。
1. 資本金が1億円超の場合
資本金:1億1,000万円
売上高:1億円
利益:1,500万円(課税所得)
資本金が1億円以上の場合、法人税率は23.2%です。したがって、法人税額は以下のように計算できます。
1,500万円×23.2%=348万円
2. 資本金が1億円以下で所得が800万円以下の場合
資本金:500万円
売上高:1,000万円
利益:200万円(課税所得)
資本金が1億円以下で所得が800万円以下の場合、法人税率は15%です。
200万円×15%=30万円
3. 資本金が1億円以下で所得が800万円を超える場合
資本金:900万円
売上高:5,000万円
利益:1,000万円(課税所得)
資本金が1億円以下で所得が800万を超える場合、800万円以下の部分は15%、800万を超える部分は23.2%の法人税率が適用されます。
800万円以下の部分:800万円×15%=120万円
800万円超の部分 :200万円×23.2%=46万4,000円
120万円+46万4,000円=166万4,000円
資本金や課税所得などにより適用税率は違います。また、実際には法人税以外にもさまざまな税金が発生すると考えられるため、正確な納税額は税理士などに相談しましょう。
【参考ページ】
国税庁 法人税
国税庁 No.5759 法人税の税率
財務省 税金には、どういった種類のものがありますか
税金に関する制度
事業活動でも正確な税金の計算は重要ですが、ここでは数ある税金の中でも消費税におけるポイントを紹介します。特に個人事業主は内容の理解と措置の検討が必要な部分なので、ここで情報を簡単に整理しましょう。
2023年10月よりインボイス制度が開始されます。この制度では原則として、買手が適格請求書等の保存をすることが仕入税額控除の要件です。適格請求書を発行するには事前に適格請求書発行事業者としての承認が必要なため、取引先へ登録が済んでいるか確認してみましょう。
原則、課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は発生しません。ですから、開業したばかりで売り上げが少ない個人事業主は、適格請求書発行事業者の登録は手間も考慮して受けないというケースもあるでしょう。しかし、取引先から見れば適格請求書の受領が仕入税額控除の要件です。適格請求書の発行が不可能となれば取引を避けられるか、消費税分の実質的な値引きを求められる可能性にも留意しておきましょう。
適格請求書は、定められた一定の事項が記載されている請求書をいいます。現在は消費税が10%と8%(軽減税率)のものが混在しているため、それらを買手に対して分かりやすく正確に伝えることが目的です。
適格請求書発行事業者になれば、課税売上高が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生します。事務負担も増加しますが、簡易課税制度を利用すれば消費税の計算が簡素化されて負担軽減が可能です。消費税は「売り上げにかかる消費税ー仕入れにかかる消費税」で計算されますが、簡易課税制度では仕入税額の計算はみなし仕入率を使って計算する方法です。みなし仕入率は事業の内容により40%〜90%の間で区分されています。
適格請求書等の保存は、電子帳簿保存法と関係があります。電子帳簿保存法では、適格請求書の写しをデジタル(電磁的記録)で保存することが認められています。しかし、保存時は改ざん防止のために一定の要件を満たさなくてはなりません。
デジタルで保存する方法はいくつかありますが、たとえばスキャナ保存における要件の一例として、以下が挙げられます。
・書類の作成や受領からおおむね7営業日以内に行う
・解像度は200dpi以上
・タイムスタンプを付与する
・保存したデータは取引の年月日や金額などで指定して検索が可能である
電子化は便利な点と注意点が両方あるため、対応する際は要件をチェックしたり専門家へ確認したりして始めましょう。
【参考ページ】
国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(PDF)
国税庁 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存(PDF)
税金に関する書類
税金に関して税務署への提出が義務付けられている資料を「法定調書」といいます。これは、報酬などの支払いについて、その金額、支払った相手や内容を報告するためのものです。法定調書は全部で60種類あり、必要に応じて入手し提出しなければなりません。
個人事業主においては、たとえば以下の法定調書が必要となることがあります。
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、弁護士や税理士に年間5万円を超える報酬を支払ったときなどに必要となるものです。税理士などに業務を委託している場合は作成を忘れないよう注意しましょう。
「不動産の使用料等の支払調書」は年間15万円を超える不動産の使用料などが発生する場合に必要です。ただし、アパートなどの賃貸借の代理や仲介業務をメインの業務として営んでいる場合は提出しなくても問題ありません。支払調書のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロード可能です。
ほかには、所得控除の内容や住民税額などが記載された所得証明書や課税証明書という書類もあります。これらは金融機関でローンの申し込みをする際などに必要です。発行を依頼する際は市区役所などに問い合わせてみましょう。
【参考ページ】
国税庁 No.7401 法定調書の種類
国税庁 No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
国税庁 No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
岡山市 よくある質問 市県民税所得・課税証明書を郵便で請求することはできますか。
節税対策
個人事業主ができる節税対策として、たとえば以下が挙げられます。
・青色申告を行う
・家賃、水道光熱費、自動車にかかる費用などを経費に計上する
・小規模企業共済に加入する
・iDecoに加入する
下記でより詳細に解説します。
1. 青色申告を行う
青色申告では、税制優遇などの特典を受けられます。青色申告とは、白色申告以外で確定申告をすることです。青色申告には事前の承認や一定の基準を満たす帳簿などの作成が必要です。経理業務の手間はかかるものの、以下のメリットを享受できます。
・青色申告特別控除
一定の基準をクリアした記帳を基に作成した貸借対照表や損益計算書を提出することで、最大55万円の控除を受けられます。さらに、電子帳簿保存もしくはe-Taxでの申告を行っている場合、その控除額は65万円です。
・青色事業専従者の給与控除
納税者と一緒に事業を営む生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、一定の要件を満たすことでその金額を必要経費に計上できます。白色申告でも事業専従者控除が適用可能ですが、必要経費に計上できる金額に明確な制限があります。
・純損失の繰越しと繰戻し
事業で純損失が発生した場合、その純損失額を翌年から3年間にわたって所得金額から控除できます。前年も青色申告を選択していれば、純損失が発生した前年に繰り戻し、前年分の所得税の還付を受けられます。
2. 家賃、水道光熱費、自動車にかかる費用などを経費に計上する
事業用に使われた家賃、水道光熱費、ガソリン代などは必要経費に計上できます。個人事業主の中には、家を居住スペースと事業用の両方で使用している人もいるかもしれません。事業用に使われた分は必要経費になるため、意識してみると節税につながる可能性があります。算出方法が分からない場合、税理士などに相談してみましょう。
3. 小規模企業共済に加入する
小規模企業共済の掛金は、その全額が所得控除の対象です。毎月の掛金は1,000円〜7万円まで500円単位で設定できます。小規模企業の経営者や個人事業主が退職金や年金として活用する制度であるため、資産を増やしつつ節税も狙えます。
4. iDecoに加入する
小規模企業共済と似ていますが、iDeCoも掛金が全額所得控除の対象です。また、資産を受け取るときも公的年金等控除あるいは退職所得控除となるため、節税効果が期待できます。
上記のようにいくつか節税が期待できるものがあります。しかし、その効果は収入の状況などにより異なるため、しっかりシミュレーションしてから始めましょう。
【参考ページ】
国税庁 No.2070 青色申告制度
国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
中小機構 小規模企業共済
iDeCo公式サイト iDeCoってなに?
税務調査
税務調査とは、簡単に言えば国税局や税務署が納税した個人や法人に対し、適切に納税しているかどうかをチェックするものです。調査の結果、納めるべき税金が適切に申告されていないことが判明した場合、修正申告で正しい金額を納税しなければなりません。
明らかに脱税が疑われている場合などはもちろんのこと、税務調査は特に不正をしていなくても行われることがあります。たとえば、税金の申告において以下が疑われる場合は税務署より確認の電話が入る可能性があります。
・計算ミス
・転記ミス
・記載漏れ
上記は故意ではないケースが多いと考えられますが、税務署から確認あるいは書類の提出が求められた場合は応じるようにしましょう。上記の軽微なミス以外にも、売り上げに対して必要経費の金額が大きすぎると判断された場合なども調査される可能性があります。
税務調査を受ける場合は、以下の点をポイントとして押さえておきましょう。
・分からない点は確認する旨を伝える
・税理士などと連携する
・守秘義務のある資料の提出は事前に確認する
税務調査では取引の内容についてだけでなく、さり気ない会話から責任者や当事者について探りを入れられることがあります。また、取引の内容についても即答が難しい質問をされる可能性も考えられます。このとき、あいまいな回答はせずにまず確認する旨を明確に伝えましょう。悪意がなくても不明瞭な回答はやましいことがあるのでは、と疑われてしまいます。
質問内容が専門的で自力での対応が難しい場合、税理士にサポートを依頼することも有効です。税務調査が来ると分かったタイミングで連携しておけばスムーズです。
税務調査では守秘義務が課された資料などの提出を求められることもあります。提出資料を作成したのが取引先などであった場合、確認と了承のために連絡を入れておくと安心でしょう。
税務調査は事前の通知がありますが、調査の対象となる明確な基準は公開されていません。修正申告を回避あるいは軽微な金額に抑えるためにも、日頃から適切な経理処理が大切です。
【参考ページ】
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
税理士の役割と活用方法
個人事業主の中には税務の専門知識がなく、税理士へお任せしたいという人もいるでしょう。税理士には主に以下の業務などを委託できます。
・領収書や請求書の整理と記帳
・確定申告
・税務に関する相談
・税務調査の立ち合い
・経営コンサル
確定申告の時期になり領収書や請求書の整理を始めることは、日頃の業務の負担増加にもつながります。また、正確な確定申告を行うためにも早い段階から専門家の力を借りた方が安心できるかもしれません。
税理士を探す方法として、たとえば以下が考えられます。
・税理士会へ相談する
・税理士紹介サービスを利用する
・知人の個人事業主などに聞いてみる
・税務のセミナーに参加する
日本税理士会連合会の公式ホームページでは、全国の税理士を検索することが可能です。ほかにも民間の税理士紹介サービスを利用したり、知り合いの個人事業主から紹介を受けたりする方法もあります。
相談にあたっては、今困っていることや税務でつまずいている点を整理して伝えてみましょう。最初は無料で簡単な相談ができるケースがあるため、その機会を生かして税理士事務所や税理士の雰囲気や対応を確認することも重要です。
【参考ページ】
日本税理士会連合会公式ホームページ
税金に関するよくある質問
税金とは私たちの暮らしを維持するために国民がみんなで出し合うお金です。警察や消防、ごみ収集、福祉などは税金により成り立っています。もし税金がなければ医療費が全額自己負担になったり、警察への相談も有料になったりするかもしれません。
税金には消費税や所得税があり、適切な金額を申告して納税することが重要です。もし申告金額に誤りや不正があれば、調査などにより正しい金額で納税するよう求められます。税務は高度な知識を要することもあるので、不明点があれば税理士に相談しましょう。
税金は、たとえば以下に使われています。
・社会保障(年金、医療)
・防衛関係
・公共事業
・地方交付税交付金
・国債税金の使い道の中でも、社会保障は「令和5年度一般会計予算」において約3割を占めています。少子高齢化が進む中で、今後も税収の重要度が高まるでしょう。
公共事業費には、たとえば設備の老朽化対策や防災・減災を目的とした技術開発などが含まれます。また、DX推進のための取り組みにも税金が使われています。上記のほかに物価高騰対策や中小企業対策などにも役立てられ、社会の維持には欠かせません。
税金を期限内に納税していない場合、納税するまでの期間に対する延滞税が発生します。もし税務署から督促状が届いても未納が続いた場合、財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
万が一納付を忘れていた場合は、すみやかに納付の手続きを行いましょう。また、申告をしたとしても、その金額が過少であった場合はペナルティとして重加算税が発生する可能性もあります。このような状態にならないよう、必要に応じて早めに税理士など専門家へ相談しておくことも大切です。
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。