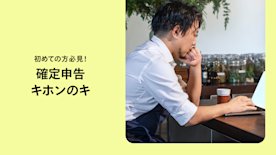個人事業主・フリーランス・自営業が納める税金の種類4つ

フリーランスや自営業者などの個人事業主が納めなくてはならない税金は、株式会社や合同会社などの法人とは異なる部分があります。本記事では、納めるべき税の具体的な種類や納税のタイミング、納めなかった場合のリスクといった基本的な情報ともに、目安となる納税額のシミュレーションなどもあわせて紹介します。
個人事業主・フリーランス・自営業が納める税金の種類
法人化せずに事業を行っているフリーランスや自営業者などの個人事業主は、大きく分けて4種類の税金を納める必要があります。具体的には「所得税」「住民税」「消費税」「事業税」です。それぞれの税の内容について、基本的な部分をチェックしていきましょう。
所得税
所得税は1年間の所得額をもとに課税される国税です。事業による所得だけでなく、利子所得や配当所得、不動産所得など、個人として得たすべての所得が対象となります。課税額の算出対象となる期間は毎年1月1日から12月31日であり、翌年の2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに所轄の税務署で確定申告を行い、税額が決定します。税率は課税対象額が多ければ多いほど高くなる累進課税制となっており、5%から45%まで7段階に分かれています。
また2013年からは、2011年3月に発生した東日本大震災から復興するために必要な財源の確保を目的とする「復興特別所得税」も課せられるようになりました。税額は「基準所得税額」× 2.1%で算出し、2037年の所得まで対象になることが決まっています。
住民税
住民税は、都道府県が課税する都道府県民税と市区町村が課税する市町村民税の総称であり、地方税に分類されます。前年の1月1日に住所や事業所を置いていた都道府県、および市町村に納める必要があります。住民税は納税者によって「個人住民税」と「法人住民税」に分けられますが、個人事業主に関わってくるのが「個人住民税」の方です。
課せられる「個人住民税」の金額は「所得割」と「均等割」という2つの異なる算出方法の合算額となっています。まず「所得割」ですが、課税所得に対する税率は都道府県民税が4%、市町村民税が6%の合計10%となっており、たとえば年間の課税所得が300万円であれば、所得割の部分の納税額は30万円となります。
一方の「均等割」は所得額に関係なく一律の金額が課せられます。都道府県民税の年額が1,000円、市町村民税の年額が3,000円というのが標準とされていますが、2014年から2023年分に関しては防災施策の財源に充てるという理由からそれぞれ年額500円が上乗せされ、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円となり、合計の年額が5,000円となっています。ただし、これらの金額は自治体それぞれの裁量によって条例で変更が効くため「地方環境税」などの名目で超過課税が行われている地域も存在します。まとめると、課税所得の10%にあたる「所得割」に「均等割」の5,000円を足した金額が個人事業主に課せられる標準的な住民税額ということになります。
ここで気をつけておきたいのが、住所と事業所を置く場所が別々の場所にあったり、事業所や店舗などが複数のエリアにまたがって存在したりする場合です。たとえば大阪市の場合、大阪市内に住んでいる人には個人市民税と府民税の均等割と所得割が、大阪市の区内に事務所や店舗があってその区内に住んでいない人には、事務所や店舗がある区ごとに個人市民税と府民税の均等割だけが課税されます。詳しくは住所や事業所がある自治体のホームページなどで確認してください。
消費税
消費税は商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される国税で、消費者が負担し事業者が納付するという様式をとる間接税の一種です。商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどが課税の対象となります。標準税率は10%ですが、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡については軽減税率の8%が適用されます。
事業税
個人事業者には基本的に事業税として個人事業税が課せられます。納付先は都道府県で、地方税のひとつです。個人事業税の対象となるのは都道府県ごとに定められた業種のみであり、該当しない業種の場合、個人事業税は課税されません。
税率は3つに分けられたそれぞれの業種区分によって異なり、3%から5%までの開きがみられます。
納税額は所得の金額をベースに算出されますが、確定申告を行うことで同時に個人事業税についても申告したこととなるため、改めて申告する必要はありません。また、個人事業税には一律290万円の控除があるので、事業所得が290万円を下回る場合には納税する必要が発生しません。
個人事業税は「事業を進めるうえで行政サービスを利用することを見越し、その経費の一部を負担する」という名目上、所得税や住民税と違って事業の運営に必要なコストとして経費計上ができます。
個人事業主・フリーランス・自営業の税金はいつ払うか
個人事業主に課せられた「所得税」「住民税」「消費税」「事業税」はいつまでに納める必要があるでしょうか。それぞれについてみていきましょう。
所得税の納付期限
所得税の納付期限は基本的に確定申告の期限となる3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)です。ただし、納付すべき金額の半分以上を納期内に納めている場合は、年率1.6%の利子税がかかりますが、残りの金額の延納が認められています。
また、一部の業種では取引先が対価を支払う際に源泉徴収しているケースがあります。支払う相手の所得税を見越して支払額に一定の率を掛けた金額を取引先が先回りして国に納税するものですが、その合計が確定申告時に決定した所得税額を上回っている場合には、その差額が還付金として戻ってきます。
住民税の納付期限
住民税は一括納付と4回に分けての分割納付があり、基本的に一括納付の場合は6月末日、分割納付の場合は6月末日、8月末日、10月末日、1月末日となります。
毎年6月に市町村から納付書が届くので、その指示に従って納付してください。
消費税の納付期限
消費税の納付期限は原則として3月31日となっており、前年分を納付します。確定申告によって税額を算出するので、確定申告提出時から3月31日までが納期となります。
個人事業税の納付期限
個人事業税にも一括納付と2回に分けての分割納付があり、原則として一括納付の場合は8月末日、分割納付の場合は8月末日と11月末日に期限が設けられています。毎年8月に市町村から納付書が届くので、その指示に従って納付してください。
【参考ページ】
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁
個人事業主は要確認!所得税の納税期限と3つの納税方法 | マネーフォワード クラウド
個人事業主・フリーランス・自営業の税金が非課税になる条件
場合によっては個人事業主が納める税金が免除されたり非課税になったりするケースがあります。どのようなケースが該当するか、それぞれみていきましょう。
所得税が非課税になる条件
所得税は所得をベースに算出するので、そもそも課税所得がない場合には非課税になります。
具体的には以下の3つのケースが考えられます。
・決算が赤字の場合
課税対象額が0円であれば、税額も0円になるため、課税されることはありません。
・青色申告をしていて前3年の赤字の繰越がある場合
確定申告をする際に青色申告を選択している個人事業主は3年間赤字を繰り越すことができます。たとえば初年度に多額の赤字を負い、2年目、3年目も相殺して赤字が続くようなケースでは所得が0円となるため、それに合わせて2年目、3年目の課税額も0円となります。
・所得金額よりも所得控除額のほうが大きい場合
所得税を算出する際には、所得から差し引くことのできるさまざまな控除が用意されています。もともとの所得がそれほど多くない場合には、いくつかの控除を適用していくと課税所得が0円になることもあり、その際は所得税が課税されなくなります。
住民税が非課税になる条件
住民税が非課税になる条件もおおむね所得税が非課税になる条件と同じですが、住民税の内訳のなかには所得にかかわらず一律で納めなくてはならない「均等割」の部分があります。
この「均等割」も含めて非課税になるケースとしては以下の条件に当てはまる場合が挙げられます。
・生活保護を受けている場合
生活保護法による「生活扶助」を受けている人は、住民税の「均等割」「所得割」の両方が非課税になります。ただし、「医療扶助」「教育扶助」といった「生活扶助」以外の扶助については対象になりません。
・未成年者、障害者、寡婦または一人親で前年の合計所得金額が135万円以下の場合
・前年の合計所得が各地方自治体の定める金額以下の場合
自治体によって異なりますが、前年の合計所得が一定の要件を満たす場合には「均等割」「所得割」の両方が非課税になることがあります。たとえば東京23区では以下が要件として挙げられています。
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円以下
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円以下
消費税が非課税になる条件
消費税について、個人事業主は課税業者になるか免税事業者になるかを選ぶことができます。免税事業者であれば消費税を納める必要はありませんが、次の条件を満たしていない場合は免税事業者にはなれません。
・基準期間(消費税の納税義務を判定する年の前々年の1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円以下
・特定期間(消費税の納税義務を判定する年の前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円以下
また、簡易課税制度を利用していない事業者で、売上にかかる消費税よりも経費にかかる消費税のほうが多かった年度については、納めるべき消費税は0円となります。
個人事業税が非課税になる条件
個人事業税が非課税になる条件については、大きく分けて4つのケースがあります。
・事業所得が290万円以下の場合
個人事業税には「事業主控除」というものがあり、1年間で290万円が控除されることになっています。営業期間が1年に満たない場合は月割制となり、ひと月あたり約24万円の控除が得られます。よって、事業所得がこれらの金額を下回る場合は課税されることはありません。
・法定業種以外の業種の場合
先にも挙げましたが、個人事業税の対象となるのは都道府県ごとに定められた業種のみであり、該当しない事業の場合、個人事業税は課税されません。一般的には、ミュージシャン、スポーツ選手、漫画家、作家などが挙げられます。詳しくは管轄の税務署で確認するとよいでしょう。
・前3年の赤字の繰り越しがある場合
所得税の場合と同様に、前3年の赤字の繰り越しがある場合は個人事業税も非課税となります。
・その他の繰越控除がある場合
白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額がある「被災事業用資産の損失の繰越控除」を受けているような場合も個人事業税が非課税になることがあります。
【参考ページ】
確定申告をしなくていい金額はいくらまで?金額や判定方法をチェック - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
個人事業主・フリーランス・自営業が税金を支払わないリスク
では、個人事業主が税を納めなかった場合、どんなリスクが生じるでしょうか。それぞれの税についてみていきましょう。
所得税を支払わなかった場合のリスク
所得税を期限内に納めなかった場合、納付期限の翌日から延滞税が発生し、納付の際は本来の税額に加えて延滞税も納めなくてはならなくなります。この延滞税の利率は所得税の場合、期限から2カ月を超えると上昇します。また、納付期限から50日以内に税務署から督促状が送られてきます。この督促状の発送日から10日以内に全額を納付しないと差し押さえが行われることになり、不動産や預貯金、株や保険といった財産が強制的に換価、処分されます。
住民税を支払わなかった場合のリスク
住民税も所得税を納めなかったときと同様のリスクがありますが、国税と地方税という違いがあることから延滞税の利率が上がるタイミングや督促状が送られる時期が異なるので注意が必要です。
延滞税の利率が上がるタイミングは納付期限から1カ月以上経過した時点に、督促状が発送されるのは納付期限から20日以内と、どちらも所得税に比べると短くなります。
消費税を支払わなかった場合のリスク
消費税を期限内に納付できなかった場合のリスクは国税である所得税の場合と同様です。
個人事業税を支払わなかった場合のリスク
個人事業税を滞納した場合のリスクは地方税である住民税の場合と同様です。
これらの実質的な不益のほかにも、風評による取引停止などもリスクのひとつとして考えられるので頭に入れておくといいでしょう。
また、税金の滞納は故意であるかどうかで税務署の対応が大きく変わってきます。悪質だと認められた場合には無申告加算税や重加算税が課せられることもあるので、放置することは避けるべきです。納める意志があるのに仕方なく納められないことが見込める場合には、早めに税務署に相談することをおすすめします。
【参考ページ】
税金が支払えない!個人事業主が知っておきたい対策や制度などをご紹介! | 起業・創業・資金調達の創業手帳
振替納付日について/期限内に納付できなかった場合は|国税庁
個人事業主・フリーランス・自営業が納める所得税はいくら?
個人事業主が納める所得税は以下のようなステップで算出します。
1. 所得を算出する
すべての収入から必要経費を差し引きます。ここで算出された額が所得となります。
2. 所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する
算出された所得から基礎控除や配偶者控除など適用可能な所得控除を差し引きます。ここで算出された額が課税所得金額となります。
3. 所得税の税率を乗じて所得税額を、さらに特定の税額控除を差し引いて基準所得税額を算出する
課税所得金額に所得税率を乗じ、所得金額を算出します。所得税率は課税所得額に応じて7段階用意されているので、その税率が対応する範囲ごとに当てはまるものを選んで計算します。
その後、住宅ローン控除や配当控除などが利用できる場合はその額も差し引くことができます。ここで算出された額が基準所得税額となります。
4. 基準所得税額をもとに復興特別所得税額を算出して、特定の税額控除を差し引き、最終的な納税額を算出する
また2013年からは、2011年3月に発生した東日本大震災から復興するために必要な財源の確保を目的とする「復興特別所得税」も課せられるようになっているので、その額も算出しなくてはなりません。税額は「基準所得税額」× 2.1%で算出します。
基準所得税額に復興特別所得税額を加えた額が納めるべき所得税額となります。
個人事業主・フリーランス・自営業が納める所得税の計算シミュレーション
では、具体的に収入が500万円だった場合の所得税額の算出をシミュレーションしてみましょう。
1. 所得を算出する
必要経費を50万円として収入から差し引きます。
500万円 - 50万円 = 45万円(所得)
2. 所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出する
所得控除を90万円として所得から差し引きます。
450万円 - 90万円 = 360万円(課税所得金額)
3. 所得税の税率を乗じて所得税額を、さらに特定の税額控除を差し引いて基準所得税額を算出する
課税所得金額に所得税率を乗じ、所得金額を算出します。
195万円×5% = 9万7,500円
(330万円 - 195万円)×10% = 13万5,000円
(360万円 - 330万円)×20% = 6万円
↓
合計:29万2,500円(所得税額)
段階ごとに計算するのが面倒な場合は、国税庁が用意している「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。
360万円×20% - 42万7,500円 = 29万2,500円(所得税額)
【参考ページ】
所得税の税率|国税庁
住宅ローン控除や配当控除などが利用できる場合はその額も差し引きます。仮に15万円人して計算します。
29万2,500円 - 15万円 = 14万2,500円(基準所得税額)
4. 基準所得税額をもとに復興特別所得税額を算出して、特定の税額控除を差し引き、最終的な納税額を算出する
14万2,500円×2.1% = 2,992.5円(復興特別所得税額)
基準所得税額に復興特別所得税額を加えた額が納めるべき所得税額となります。
14万2,500円 + 2,992.5円≒14万5,492円(1円未満の端数金額は切り捨て)
【参考ページ】
No.2260所得税の税率|国税庁
個人事業主・フリーランス・自営業の税金対策
個人事業主の税金対策にはどのようなものがあるでしょうか。比較的高い節税効果が見込める所得税について、主だったところを紹介します。
青色申告を利用する
確定申告時に青色申告を選択すると、単式簿記で10万円、複式簿記で65万円の控除が受けられます
必要経費を正確に把握し、計上する
たとえば自宅を事業所としている場合、家賃や光熱費などを按分して計上することができます。また自動車などを事業で使うことがある場合には、燃料代のほか自動車保険料や車検費用なども利用割合に応じて計上可能です。このような細かな経費も漏らさず積み上げることによって収入から差し引くことができる必要経費が正確に把握でき、節税につなげることができます。
少額減価償却資産の特例を活用する
資本金が1億円以下で従業員が500人以下の青色申告をしている個人事業主の場合、固定資産の取得価格が30万円未満で年度内での合計額が300万円未満のときは、「少額減価償却資産の特例」を適用することによって、その年度にまとめて減価償却することができます。これにより、耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果が得られます。
小規模企業共済制度などに加入する
将来の退職金がわりに銀行の定期積立預金などを利用すると課税対象となりますが、小規模企業共済に加入すれば、掛金は全額所得控除になります。同様に中小企業倒産防止共済や国民年金基金、iDeCoなども所得控除の対象となるので、あわせて検討するとよいでしょう。
個人事業主・フリーランス・自営業が納める消費税とインボイス制度
2019年10月からの消費税率引き上げにより、標準税率である10%の商品と軽減税率である8%の商品が混在するようになりました。そのような状況のなかで正しく消費税額を把握し、正確に納税してもらうことを目的のひとつとして、商品それぞれに価格と税率を記載した適格請求書、いわゆるインボイスを発行、保存する制度(インボイス制度)が2023年10月1日から始まりました。
消費税は間接税であり、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費したりサービスの提供を受けたりする消費者が負担することとなります。納税の際は、生産や流通などの各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、事業者は課税売上げに係る消費税額から課税仕入れなどにかかわる消費税額を控除した金額を納める仕組みで、税が累積しないようになっています。
ここで問題となっているのが、先に紹介した消費税を納める必要のない個人事業主である免税事業者が介入する場合です。
一連の取引がすべて課税事業者だけで完結する取引であれば、消費者が負担する消費税とそれぞれの事業者が納める消費税の合計は原則一致するはずです。しかし、課税事業者がインボイスを発行できない事業者(免税事業者)から仕入をした場合は仕入税額控除が受けられなくなり、免税事業者が本来負担すべきはずの消費税も加えて納税しなくてはならなくなってしまいます。フリーランスや自営業者など、免税事業者の取引先が課税事業者である場合、仕入税額控除を受けられないことを理由に取引を断られたり消費税分の値引きを要求されたりする可能性も考えられます。
そのような状況のなか、現在、免税事業者である個人事業主には、消費税を納める必要のない免税事業者のままでいるか、課税事業者に切り替えるかの選択が迫られています。
2023年10月1日からのインボイス制度導入にあたり、事業者にはさまざまな負担が生じることが見込まれます。そこで政府はいくつかの経過措置を設けました。「持続化補助金の加算」「会計ソフトの導入に対する補助金」「特定の取引を対象外にする」といったものもありますが、なかでも大きな負担軽減策と考えられるのが、いわゆる「2割特例」です。「2割特例」とは、2023年10月1日から2026年9月30日の間、これまで免税事業者だった事業主がインボイス制度に対応した場合、その課税期間中に納める消費税額を売上税額の2割にできるというものです。
また経過措置以外にも、仕入税額控除の計算を簡素化し、事務処理にかかる業務負担や費用負担を軽減することを目的とした「簡易課税制度」というものもあります。税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで導入できるもので、「売上にかかる消費税額 - 仕入にかかる消費税額」を正確に計算する(本則課税)ではなく、「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率」によって算出します。「みなし仕入率」は事業内容によって6つに分けられており、40%から90%までの開きがあります。
個人事業主・フリーランス・自営業が納める税金関連記事
個人事業主・フリーランス・自営業が納める税金に関するよくある質問
基本的には「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の4つです。「消費税」については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなど売上の規模が小さい場合は、納税する必要のない免税事業者になることも選択できます。
所得税がかからないため条件には所得が0円かマイナスでなくてはならず、一概に年収の額を算出することはできません。ただし、確定申告の際、所得が2,400万円以下の場合の基礎控除額が48万円であることから、総所得が48万円以下であれば所得税がかからないということができます。
確定申告時に適用可能な控除の数や種類によっても差が生じるため、はっきりとした数値を出すことはできませんが、1000万円の所得がある人の場合、所得税と復興特別所得税を合わせて年額120万円程度が大まかな目安として挙げられます。
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。