※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
現在、個人事業主として事業を営んでいる経営者の中には、事業の法人化に関心のある人もいるでしょう。個人事業主と法人は法務や税制の違いがあり、どちらにもメリットとデメリットが存在します。
本記事では、個人事業主と法人の違いを整理し、法人化に適切なタイミングを解説するとともに、法人化のメリット・デメリット、手続きの方法まで詳しく解説します。またあわせて、法人化に向けて参考になるサービスも紹介します。
目次
- 個人事業主と法人の違い
・法的な違い
・税制の違い
・社会的信用の違い - 個人事業主から法人化を検討する理由
・法人化を考え始めるタイミングとは? - 個人事業主が法人化するメリット
・社会的信用の向上
・節税効果
・事業拡大のしやすさ
・責任範囲の限定 - 個人事業主が法人化するデメリット
・設立・運営コストの増加
・事務手続きの負担 - 法人化の具体的な手続き
- 法人化のタイミングに合わせてSquareで業務効率化!
- まとめ
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人では、法的な違いのほか、税制面、社会的信用面でも違いがあります。それぞれ見ていきましょう。
法的な違い
個人事業主と法人の法的な違いとして代表的なものに、設立手続きと責任の範囲があります。
個人事業は、税務署に開業届を提出し、都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」を提出すれば開始できます。手続きにそれほど時間はかからず、開業資金以外の費用もとくにかかりません。一方、法人の設立には定款の作成や、法務局での登記手続きが必要です。これらの手続きは煩雑で、所定の費用が発生します。
責任の範囲については、個人事業では事業の成果も債務もすべて経営者個人に帰属しますが、法人では会社と個人の財産は区別されます。会社が倒産したときには出資額は失いますが、出資額以上の責任は負いません。
税制の違い
個人事業主と法人では、事業で得た所得の扱いが異なります。個人事業主の場合は、個人の所得として所得税の対象です。それに対して法人の所得は、経営者の取り分とは分離され、法人税が課されます。
また、所得税は所得金額が高くなるほど税率も高くなる累進税率が適用される一方、法人税は税率が一定である点も大きな違いです。この税率の違いが法人化の可否を判断する重要な基準の一つとなります。
なお、個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日ですが、法人の事業年度は1月~12月でなくても構いません。年度初めを4月、決算月を3月とする会社が多くみられますが、決算期と繁忙期をずらすなど柔軟に調整するとよいでしょう。確定申告は事業年度末から2カ月以内に行います。
社会的信用の違い
個人事業主よりも法人のほうが社会的な信用力が高いといわれています。法人は登記によってその存在が公的に認められるうえ、基本的な情報が一般公開されて透明性に優れるためです。
社会的信用力は金融機関からの融資や大きな取引にも影響を及ぼします。信用力が高いと、融資の際には一度に借り入れられる金額や審査の通りやすさの面で有利です。個人事業主でも融資が受けられないわけではありませんが、法人に比べてハードルは高いといえます。
また、企業は、大きな取引になるほど、取引先として信頼に値するかどうかを重視します。法人であれば登記情報が判断材料の一つになりますが、個人事業主は証明がなかなか難しく、個人との契約を避け、取引先を法人に限定する企業もみられます。

個人事業主から法人化を検討する理由
個人事業主が法人化を具体的に考え始めるタイミングとしては、売り上げが伸びて税負担が大きくなったときや、取引先から法人格を求められたときなどがあります。
法人化を考え始めるタイミングとは?
売り上げが順調に伸びて所得税の納税額が大きくなっている場合、あくまで目安ですが、課税所得が安定して800万円~900万円の水準に達しているなら法人化を検討してもよいでしょう。課税所得は、簡単に示すと売り上げから経費と所得控除額を引いた金額を指します。所得控除について詳しくは、国税庁のウェブサイトを確認してください。
個人の所得税は5%~45%の累進税率が適用されます1。また、所得税のほかには復興所得税(2.1%)と住民税(10%+均等割)が課されます。
| 課税される所得金額 | 税率 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
法人税率では、年間所得が800万円を超える場合の税率は、800万円以下の部分が15%、800万円超の部分は23.2%です2。加えて、法人住民税、法人事業税なども負担します。これらの税目を合計し、事業税の損金算入を考慮した実際の税負担の程度を示す「実効税率」は、約30%(800万円を超える部分)といわれています。
| 課税される所得金額 | 税率 |
| 8,000,000円まで | 15% |
| 8,000,000円超え | 23.2% |
法人の税負担が個人事業主の税負担を下回るのは、概算でいうと課税所得が800万円~900万円の水準です。売り上げが伸び、この水準以上の課税所得を安定して維持できるようなら法人化を検討したほうがよいでしょう。
次に、法人格との取引を求める企業や団体との契約を検討している場合も、法人化が不可欠となります。大きな契約金額になる、機密情報を扱う、仕様が厳密で責任が大きいなどの取引では、法人格が必須となる場合も少なくありません。
最後に、従業員を採用したい場合も、法人化を検討するタイミングといえます。個人事業では、厚生年金や健康保険への加入は従業員が常時5人以上になったときです。一方、法人は経営者1人であっても厚生年金と健康保険に加入します。求職者にとっては、似たような条件であれば法人のほうが個人事業主よりも就職先として信頼でき、採用率・定着率を高めることができます。
個人事業主が法人化するメリット
法人化のおもなメリットとしては、社会的信頼、節税、資金調達や人材採用面のほか、責任範囲の限定によるリスク軽減が挙げられます。
社会的信用の向上
法人を設立するには法務局での法人登記が必要です。登記によって、組織としての体系が確立しており、法的な枠組みに則って活動しているとみなされるため、個人事業主よりも社会的信用力が向上します。
また、登記簿には社名や住所、事業の目的、代表者名、資本金額、設立日など会社の基礎的な情報が記載され、手数料を払えば誰でも会社の情報を閲覧できます。公的機関での会社情報の公開は、取引先や金融機関からの信頼を獲得する助けとなるでしょう。したがって、企業との取引や融資の審査などの面では個人事業主よりも有利になる可能性が高まります。
節税効果
課税所得が一定以上になると、個人事業主の所得税額等よりも法人税額等のほうが小さくなります。
さらに、法人は、個人事業主よりも経費として認められる費用の範囲が広い点も見逃せません。売上高が同じなら、経費が多いほうが所得は小さくなり、節税につながります。
個人事業主では経費にならないが、法人では経費にできるものの代表例が経営者の報酬・退職金です。個人事業主では売上高から経費を差し引いた分が事業所得となり、事業主自身の収入となります。一方、法人における経営者の収入は、法人から受け取る役員報酬です。役員報酬は給与として経費計上できるうえ、給与所得者は給与収入から一定の控除を受けられる「給与所得控除」が適用されます。給与所得控除の詳細は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。
さらに、法人では家族に支払う給与も全額経費にできます。個人事業主が家族に支払った給与を経費とするには一定の要件があります3が、法人は全額を経費に算入できるうえ、その年収が一定額以下であれば配偶者控除や扶養控除の対象にもなります。ただし、家族を役員とする場合は支払額や手続きに注意が必要です。また、法人の役員への退職金も、支給額や手続きで注意すべき点はあるものの、経費として計上できるため節税につながります。
事業拡大のしやすさ
事業を拡大するとなると、多くの資金や人手が必要になるでしょう。法人化すると、金融機関からの融資が受けやすくなるほか、調達方法の幅も広がります。
融資については社会的信用が高い法人のほうが一般的には審査に通りやすいといえます。また、株式会社の法人であれば、株式発行による資金調達が可能です。
株式とは、株式会社(企業)が資金調達のために発行する証券です。株式の発行によって得た資金は、金融機関からの借入金とは違って返済義務がありません。出資者は資金が返済されない代わりに、保有する株式の割合に応じた議決権を持ち、経営に参加できます。
人材採用も、求職者視点では、法人のほうが個人事業主より信頼されやすく、有利になります。法人は社会保険への加入が義務づけられているほか、福利厚生が個人事業より整っているところも多く、さらには「会社員」としての地位を得られる点も、求職者にとってのメリットとなります。
責任範囲の限定
個人事業主と法人では、法的な違いとして責任範囲に差があります。責任範囲の大きさは、事業が破綻したときのリスクの大きさに影響します。
有限責任の法人であれば、会社が倒産しても債権者に対して出資額以上の責任を負いません。有限責任を負う者で構成される法人の形態としては、株式会社と合同会社が該当します。
一方、無限責任だと会社が倒産したときには会社の債権者に対して負債の全額を弁済する責任を負います。会社で全債務を支払いきれない場合、個人の資産を持ち出してでも弁済の責任を果たさなければなりません。このような無限責任が認められている経営形態としては、個人事業主のほか、合名会社と合資会社が該当します。
とはいえ、株式会社や合同会社でも、社長が事実上の無限責任を負っている会社が少なくありません。中小企業が金融機関から融資を受ける際、社長個人の保証(経営者保証)を求められるケースが多いからです。その場合は会社が債務を返済できなくなったときには、社長個人が債務を肩代わりすることになります。
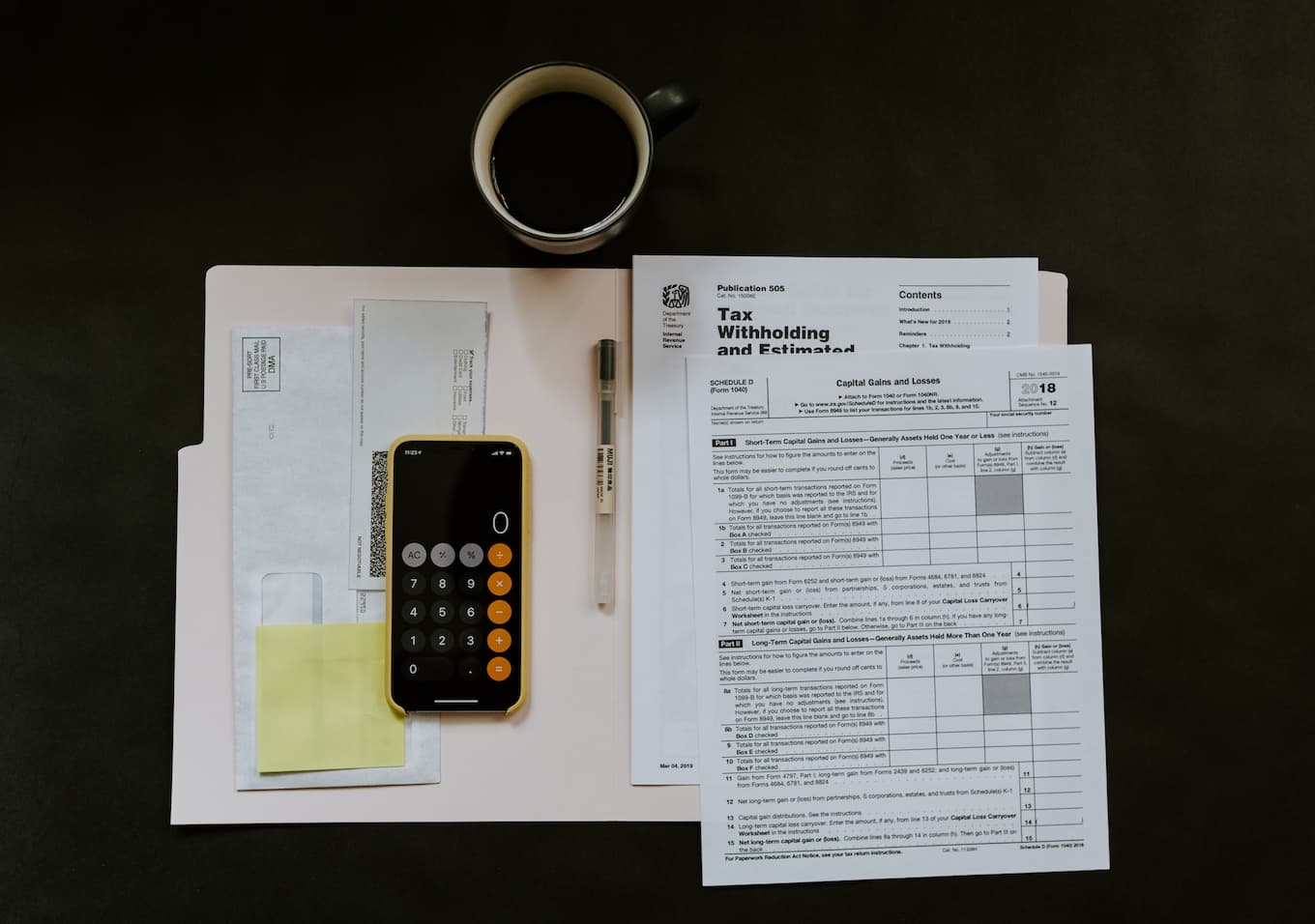
個人事業主が法人化するデメリット
法人化を行う場合、設立・運営時のコストと、税務や社会保険などの事務手続きといった負担がかかることには注意が必要です。
設立・運営コストの増加
個人事業の開業では特別な費用がかかりませんが、法人の設立には公証役場や法務局での手続きにおいて所定の費用が発生します。
公証役場に支払う費用は以下のとおりです。
| 定款認証手数料4 | 資本金が100万円未満の場合:3万円 資本金が100万円以上300万円未満の場合:4万円 その他の場合:5万円 |
| 定款印紙代(電子定款の場合は不要) | 4万円 |
| 定款謄本代6 | 謄本1枚につき250円(8枚で2,000円) |
なお、合同会社は定款作成が不要なため、公証役場への支払いは株式会社の設立時に発生します。次に、法務局での法人登記では登録免許税7を支払います。
| 株式会社 | 資本金の1,000分の7または15万円のいずれか高い金額 |
| 合同会社 | 資本金の1,000分の7または6万円のいずれか高い金額 |
株式会社には決算公告が義務づけられており、公告の方法によっては費用が生じます。決算公告とは、前年度の決算内容の要旨を広く伝えるため、官報や日刊新聞などに掲載することです。
会社の公式ウェブサイトなどインターネット上での公開は無料ですが、官報に掲載するなら最低でも8万2,000円8はかかります。なお、公告を怠ると100万円以下の過料に処するとの罰則も定められています。
そのほか、決算書の作成を税理士に依頼する予定であれば、税理士報酬もコストとして見込んでおきましょう。
事務手続きの負担
法人税の申告は個人事業主の確定申告よりも様式が煩雑で事務作業の負担が増え、社会保険の加入手続きも発生します。
法人の納税申告としては、法人税、消費税、地方法人税、法人事業税、法人住民税などが挙げられます。これらすべての申告の基となる書類が法人税申告書です。作成にあたり複数の書類、別表、添付書類が必要となり、とくに別表の作成や添付書類の準備など、事務業務には手間と時間を要します。費用はかかりますが、税務のプロである税理士への依頼も検討するとよいでしょう。
続いて、法人は雇用人数や雇用の有無に関わらず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必須です。手続きは日本年金機構の事務センターまたは事務所の所在地を管轄する年金事務所へ加入申請を行いましょう。郵送や窓口持参のほか、電子申請も受け付けています9。
なお、社会保険に関しては手続きだけでなく社会保険料の負担も発生します。健康保険と厚生年金を合わせて、給与金額の約30%が社会保険料の負担額です。これを会社と従業員とで折半するため、実際には給与の約15%10を会社が負担することになります。

法人化の具体的な手続き
個人事業の法人化における手続きを大きく3ステップに分けて紹介します。
1)会社形態を決める
有限責任でリスクを抑えられる点から、会社形態は株式会社または合同会社がおすすめです。合同会社は株式の上場ができませんので、上場を目指すなら株式会社を選びましょう。上場はしばらく考えておらず、設立費用を抑えたいなら合同会社が現実的かもしれません。出資者が複数いる場合は、意思決定や利益の分配について専門家に相談したうえで判断しましょう。
2)登記手続き(定款作成、公証役場、法務局)
株式会社を設立する場合、まず定款を作成します。定款は会社の規則をまとめたものです。不安があれば司法書士に作成を依頼するのも一つの方法です。
作成した定款を公証役場で認証してもらったら、資本金を発起人の銀行口座に振り込みます。法人登記では資本金の払い込みを証明する書面を要するためです。資本金を振り込んだら、払込証明書と通帳のコピーを添えて書類を作成しましょう。必要書類がすべて揃ったら、法務局に設立登記を申請します11。同時に、実印の登録も行えます。
3)税務署・自治体への届け出(法人設立届出書など)
登記に関する手続きを終えたら税務署と自治体へ各種書類を届け出ます。税務署に提出する代表的な書類は以下のとおりです。
- [手続名]個人事業の廃業届出等手続(国税庁)
- [手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続(国税庁)
- [手続名]内国普通法人等の設立の届出(国税庁)
- [手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)
- No.6629 消費税の各種届出書(国税庁)
- No.5100 新設法人の届出書類(国税庁)
- [手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 (国税庁)
これらすべてを提出しなければいけないわけではありません。源泉所得税や消費税関係の届け出などは必要に応じて行いましょう。自治体への提出書類は、各自治体のウェブサイトで確認できます。このほか、社会保険や労働保険の手続きも必要です。税理士や社会保険労務士に依頼すれば手続きを代行してくれます。
請求書の作成から送信まで簡単スピード対応
Square 請求書は決済機能付きのクラウド請求書サービスです。無料ではじめられ、自動送信や定期送信など便利な機能も盛りだくさん。フリーランス、個人事業主、業務請負やサービス請負業の請求業務を簡単に効率化できます。
法人化のタイミングに合わせてSquareで業務効率化!
書類作成や手続き、事務作業の負担が大きい法人化の際にも事業を滞りなく運営するためには、経理や総務などバックオフィス業務を効率化しておくとよいでしょう。具体的には、ペーパーレス化や業務の自動化などが挙げられます。
ペーパーレス化
紙の文書・書類を使っている業務の電子化は、業務効率化やコスト削減を期待できます。たとえば毎月の請求業務を紙での郵送からメール送信に切り替えれば、郵送作業にかかる手間や、用紙代・プリンタのインク代・切手代を削減できるでしょう。
Squareでは、パソコンやスマートフォンで請求書を作成・送信できるSquare 請求書を提供しています。印刷・郵送の必要がないうえ、請求書の自動送信などバックオフィス業務の自動化にもつながる機能が豊富です。
業務の自動化
経理や在庫管理、顧客管理などはソフトウエアなどの利用で自動化を図れます。例として、ECサイトを無料で作成できるSquare オンラインビジネスや、実店舗で利用できるSquare POSレジを使うと、どの商品が・いつ・いくつ・どこで売れたかがリアルタイムで在庫情報に反映されます。Squareの在庫管理機能も併用すれば在庫管理はさらに簡単になり、ECサイトと実店舗の在庫を自動的に一括で管理できるため、バックオフィス業務を飛躍的に効率化できるでしょう。
まとめ
個人事業主と法人では、税制を中心に法的な扱われ方が大きく異なります。法人化については課税所得額、事業の状況を考慮し、必要に応じて税理士など専門家の助言を受けながら判断していきましょう。
あわせて、事業に集中して売り上げを伸ばしていけるよう、バックオフィスの効率化も大切です。業務を自動化・効率化できる機能を豊富に取り揃えたSquareの活用も、ぜひご検討ください。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2018年4月26日時点の情報を参照しています。2025年5月26日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。 Photography provided by, Unsplash
1:No.2260 所得税の税率(国税庁)
2:No.5759 法人税の税率(国税庁)
3:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(国税庁)
4:会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会)
5:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(国税庁)
6:公証人手数料令(e-Gov)
7:No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)
8:官報公告料金表(掲載にかかる費用総額)(株式会社兵庫県官報販売所)
9:新規適用の手続き(日本年金機構)
10:給与からごっそり天引き 社会保険料って何? #くらしと経済(2024年9月20日、Yahooニュース)
11:商業・法人登記の申請書様式(法務局)

