摘要とは?意味や備考との違い、3つの目的、書き方のルール
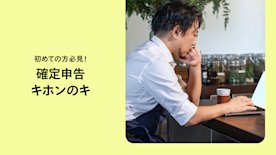
事業を手がけるにあたり、会計帳簿や請求書、領収書など、さまざまな帳簿・書類を作成します。会計帳簿や請求書、領収書などには摘要を記載する箇所があります。帳簿や書類では取引年月日や金額などに注目が行きがちですが、実は、摘要には重要な意味があります。ここでは、摘要の意味や書き方のルール、備考との違いなど詳しく解説します。
摘要とは?
摘要は、英語では「summary」などと表現され、要約や概要などの意味があります。帳簿や書類には取引先や金額などを記載しますが、それだけでは何に使ったお金なのかわからないことも多いです。そこで、摘要欄にお金の用途に関する情報を書き加えます。また、特記事項などがある場合も、摘要に記載します。基本的に摘要には、その取引において重要なことがらを記載します。
摘要と備考の違い
摘要と似ている意味の言葉として「備考」があります。備考とは、その名の通り、備えや参考として記載する事項を指します。摘要と備考を同じ意味合いのもので使っているケースもありますが、基本的には、次のような違いがあります。
摘要:取引の内容がわかるように要点を記載したもの
備考:覚書として参考程度に記載するもの。取引の内容や要点がわからなくてもよい
例えば、固定資産台帳には摘要欄と備考欄があります。摘要欄には「〇〇工務店 改修費」や「○年 減価償却費」など、内容がわかるように記載します。備考欄には、事業専用割合や必要経費算入額を記載します。備考欄だけでは、取引の内容がわかりません。
会計帳簿によっては、摘要欄しかないものもあります。作成する帳簿や書類によって、摘要と備考を使い分けましょう。
【参考ページ】
帳簿の記帳のしかた|国税庁
領収書・請求書・見積書における摘要の役割
次に、領収書や請求書、見積書における摘要について見ていきましょう。領収書や請求書、見積書は会社によってフォーマットが異なります。ここでは、一般的な形式における摘要の役割を解説します。
領収書や請求書、見積書における摘要は、それぞれ以下のようになります。
・領収書
領収書における摘要とは、但し書きのことです。領収書では、相手先名や金額、取引年月日の記載と但し書きの記載が必要です。相手先名や金額では、何に対する領収書なのかがわからないため、但し書きには取引内容を記載します。例えば、ノート代や書籍代など、販売した商品を記載します。
・請求書
請求書には、相手先名や金額、取引年月日のほかに品目(名目)欄があります。品目(名目)欄には、販売する商品名や提供するサービス名などが記載されているため、そこで取引内容がわかります。そのため、一般的に摘要は不要です。請求書では、摘要欄の代わりに備考欄があります。補足事項がある場合は、備考欄にその内容を記載します。
・見積書
見積書の摘要も、請求書と同じ取り扱いとなります。見積書には、相手先名や金額、取引年月日のほかに、品目(名目)欄があります。品目(名目)欄には、販売する商品名や提供するサービス名などが記載されているため、そこで取引内容がわかります。そのため、一般的に摘要は不要です。
見積書には、摘要欄の代わりに備考欄があります。補足事項がある場合は、備考欄にその内容を記載します。
【参考ページ】
経理担当者必見! 領収書の但し書きで気をつけるべきポイントと正しい記入方法
請求書の基礎知識
見積書の書き方・作り方を見本つきで解説!
摘要のルールと注意点
摘要には売上や経費、消費税についてそれぞれ記載ルールがあります。ここでは、それぞれの記載ルールや注意点を解説します。
1.売上
売上について、以下の項目を記載します。
① 取引の年月日
② 売上先その他の相手方
③ 品名その他給付(サービス)の内容
④ 数量
⑤ 単価と金額
⑥ 1日の売上の合計
帳簿付けの際、6つの項目を満たす必要がありますが、納品書控や請求書控などで取引内容を確認できる場合は、取引相手ごとに1日の売上合計金額のみを一括記載してもかまいません。また、小売業などで現金売上の場合も、1日の売上合計金額のみの一括記載でOKです。
帳簿によって、摘要に記載する項目は異なります。例えば、売掛帳は相手先ごとに記帳するため、相手先名を摘要に書く必要はありませんが、仕訳帳など相手先を書く欄がない帳簿は、摘要に記入します。
仕訳帳の摘要欄には「売上先その他の相手方」や「品名その他給付(サービス)の内容」を記入します。例えば「〇〇株式会社へA商品1万円を10個販売」となります。
2.経費
経費について、以下の項目を記載します。
① 福利厚生費や消耗品費、地代家賃、水道光熱費など取引内容に応じて科目に区分
② 各取引の年月日
③ 事由
④ 支払先
⑤ 金額
ただし、少額費用については、科目ごとに1日の合計金額を一括で記載するだけでもかまいません。上記のうち「事由」と「支払先」を摘要欄に記載します。例えば「〇〇文房具店 ノート代」などと記載します。
今回ご紹介した売上や経費の記載内容は、所得税の青色申告の記載事項に基づいています。摘要の内容については、細かくなりすぎないように注意しましょう。
法人で接待飲食がある場合は、お店の名前や会食相手、人数などを記載するなど、勘定科目や状況によっては、上記の①~⑤以外の項目も記載したほうが望ましいことがあるので注意が必要です。必要項目が記載されていれば、摘要の書き方は自由ですが、複数の人が帳簿付けする場合は、書き方のルールを決めておいた方が良いでしょう。
3.消費税
消費税の仕入税額控除を受けるには、帳簿に以下の事項を記載しなければなりません。
① 取引の相手方の氏名・名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 取引金額
上記のうち「取引の相手方の氏名又は名称」と「取引内容」を摘要欄に記入します。ただし、消費税だからといって特別に記載しなければならない内容はなく、上述の売上や経費と同じように摘要を記載します。また、軽減税率対象品目があれば、その旨がわかるようにします。
摘要はわかりやすく記載することが前提ですが、簡略化できるケースもあります。例えば、1回の取引で複数の商品を購入した場合は、「文房具など」としてもかまいません。また、得意先など、毎月継続して月ぎめで取引のある業者の場合は、1か月の取引をまとめて「〇月分」とできます。
4.インボイス制度導入後の摘要
納税者が消費税の課税事業者(適格請求書発行事業者)の場合、インボイス制度導入後には、帳簿付けでさらに気を付けることがあります。インボイス制度にはいくつかの特例があり、その特例によって帳簿の記載内容が異なります。代表的なものには次のものがあります。
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、取引先からインボイス(適格請求書)を受け取る必要があります。
しかし、インボイスの受け取りができないケースもあります。例えば、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送は、インボイスの交付が免除されています。このような場合は、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この場合の記載内容は、次のとおりです。
① 取引の相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨も記載)
④ 取引金額
⑤ 取引先の住所(鉄道など国税庁長官が指定する業者は記載不要)
⑥ 特例の対象となる旨
摘要に関係するのは「取引の相手方の氏名又は名称」「取引内容」「取引先の住所」「特例の対象となる旨」です。例えば「〇〇鉄道 電車代 公共交通機関特例」などと記載します。
※公共交通機関は、国税庁長官が指定する業者のため、住所の記載は不要
・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
インボイス制度では、取引先からインボイス(適格請求書)を受け取らないと、仕入税額控除を受けることができません。取引先が免税事業者の場合、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者への支払いは原則、仕入税額控除ができません。
ただし、インボイス制度の開始から一定期間は、免税事業者への支払いであっても、仕入れ税額の一定割合を仕入税額控除することができます。免税事業者への支払いに対し、インボイス制度開始から3年間は課税仕入れの80%について、次の3年間は課税入れの50%について、仕入税額控除の計算対象とできます。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置を適用するためには、摘要に「80%控除対象」というように、経過措置の対象であることがわかるように記載する必要があります。
摘要の書き方と記入例
摘要の書き方は帳簿の種類によって異なります。所得税の青色申告で55万円の青色申告特別控除を受けるためには、最低限次の帳簿を備え付けなければいけません。
① 仕訳帳
② 総勘定元帳
③ 現金出納帳
④ 売掛帳
⑤ 買掛帳
⑥ 経費帳
⑦ 固定資産台帳
それぞれについて、摘要の書き方を見ていきましょう。
・仕訳帳、総勘定元帳
仕訳帳と総勘定元帳は主要簿となるものです。仕訳帳は取引を発生順に記載するもので、借方と貸方に勘定科目を記載します。総勘定元帳は勘定科目別に分類した帳面で、仕訳帳を基に作成されます。
基本的に、仕訳帳と総勘定元帳は、摘要の記載内容は同じです。「取引の相手方の氏名又は名称」と「取引内容」を記載します。例えば、次のように記載します。
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 4月1日 | 消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | 〇〇商店 テーブル代 |
・現金出納帳
現金出納帳とは、現金の取引をすべて記載する帳簿です。入金も出金もすべて現金出納帳に記載します。現金出納帳における摘要の記載内容は「取引の相手方の氏名又は名称」と「取引内容」です。例えば、次のように記載します。
| 日付 | 摘要 | 入金(現金売上) | 入金(その他) | 出金(現金仕入) | 出金(その他) | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 現金仕入 〇〇商店 飲料水 100個x100※ | 10,000 | ||||
| 4月15日 | 修繕費 〇〇株式会社 | 30,000 | 238,210 |
・売掛帳、買掛帳
売掛帳や買掛帳は掛取引による売上や仕入の発生、掛代金の回収や支払について記載する帳簿です。相手先ごとに作成し、取引内容も掛取引によるものと決まっているため、品名欄はありますが、摘要欄はありません。そのため、摘要の記載は不要です。
・経費帳
経費帳は仕入以外の経費について記載する帳簿です。経費の勘定科目ごとに作成します。
経費帳における摘要の記載内容は「取引の相手方の氏名又は名称」と「取引内容」です。例えば、次のように記載します。
消耗品費
| 日付 | 摘要 | 金額(現金) | 金額(その他) |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 電球2個x300 〇〇商店 | 600 | |
| 6月15日 | ノートパソコン 〇〇電気店 | 80,000 |
・固定資産台帳
固定資産台帳とは事業で使用している機械や備品など、事業用の固定資産について記載した帳面で、固定資産ごとに作成します。固定資産台帳はその他の帳簿と異なり、固定資産の状況を記載します。金額も取得時の価額や現在の価額、必要経費の算入額などを記載していきます。そのため、摘要欄も固定資産の状況についての記載となります。固定資産台帳の摘要には「店舗購入」や「〇年減価償却費」「改修費 〇〇工務店」などを記載します。
【参考ページ】
帳簿の記帳のしかた|国税庁
摘要に関するよくある質問
帳簿や書類では取引先や金額などを記載しますが、それだけでは何に対する代金なのかがわからないことも多いです。
そこで重要になるのが摘要です。摘要として内容がわかりやすいように、情報を書き加えます。また、特記事項などがある場合も、それがわかるように記載します。摘要は基本的に、その取引において重要なことを記載します。
摘要と似ている意味の言葉として、備考があります。備考は、覚書として参考程度に記載するものです。取引の内容や要点がわからなくても良いものとなっています。帳簿や書類によっては、摘要でなく備考しかないものもあります。状況に応じて使い分けましょう。
摘要を記入する目的は「取引内容を明確にする」「税法上において必要なため」「第三者が確認できる」の3つです。
会計帳簿に勘定科目や金額を記載しただけでは、その取引がどのようなものかがわかりません。摘要に取引内容を記載することで、どのような取引であるのかを明確にできます。後で取引内容を確認する際にも、内容が把握しやすくなります。
また「整然と、かつ明瞭に記録」するという帳簿のルールを満たすため、あるいは消費税の仕入税額控除を受けるためには、摘要に必要事項を記載する必要があります。
さらに、税務調査や顧問税理士など、第三者が帳簿を確認することがあるため、第三者がみてもわかるように摘要を記載しなければなりません。
税法では帳簿の記帳方法について、いくつかの定めがあります。その中に、摘要に記載すべき事項も決められています。
摘要に必要な記載がなければ、経費に認められない可能性があったり、消費税の仕入税額控除が受けられなかったりと、納税者にとって不利なことがあります。忘れずに摘要を記載しましょう。
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。




