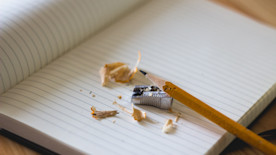確定申告とは?対象者、手続き方法、必要書類をわかりやすく解説

1年間に所得がある人は原則、確定申告をする必要があります。しかし、すべての人が確定申告をする必要はなく、対象となる人は決まっています。また、所得の種類によって、税金の計算方法や手続き方法などが異なります。
ここでは、確定申告の概要や対象者、手続き方法、必要書類などをわかりやすく解説します。
確定申告とは?
はじめに、確定申告とはどのようなものかを見ていきましょう。
確定申告とは、簡単にいうと、個人が1年間に得た売上やかかった経費、もうけ(所得)、税金を計算して、税務署に申告することです。
わが国の税金の課税方式には「賦課課税制度」と「申告納税制度」の2つがあります。賦課課税制度とは、国や自治体が納める税額を計算し、納税者に伝える制度です。代表的なものには、固定資産税や個人住民税などがあります。一方、申告納税制度とは、納税者が自ら納める税額を計算し、税金を納付する制度です。
所得税は申告納税制度を採用しています。そのため、所得税の納税者は自分で納める税額を計算し、国に申告をします。所得税の申告を「確定申告」とよんでいます。
【参照ページ】 4.申告納税制度|国税庁
個人事業主とは何かの説明
個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことです。1年間に所得を得た個人は原則、確定申告をする必要があります。
実は、確定申告が必要な個人には、個人事業主の人と個人事業主でない人がいます。個人事業主であるかどうかで、税金の計算方法や手続きの方法が異なります。そこで、確定申告をする人は、個人事業主とは何かを知っておく必要があります。
個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人と述べましたが「事業」とは何でしょうか。ここでいう「事業」とは、独立・反復・継続した仕事のことです。
例えば、自分で(独立して)お店を経営している人は、同じ仕事を反復して行います。また、毎年継続して商品の販売やサービスの提供をしています。そのため、この仕事は独立・反復・継続に当てはまり、事業になります。一方、不要なものを一度や二度、オークションで販売したケースは、反復や継続はしていないので事業にはなりません。
個人で小売業や建設業を行っている場合など、皆が思い浮かべる代表的な仕事をしているケースでは、多くの場合で事業に該当します。そのため、これらの仕事をしている人は個人事業主になります。
確定申告の目的と重要性について
次に、確定申告の目的と重要性について見ていきましょう。
確定申告の目的とは、国が税金を徴収するためであることはもちろんですが、民主的な税制度として、適正で公平な課税を重要視しており、「納税者が自らの所得や税金を正しく計算して申告する」ことを目的としています。
個人一人ひとりが高い納税意識を持ち、納税義務を自発的・適正に履行することで、申告や納税の漏れや不正をなくし、適正で公平な課税をすることができます。
確定申告の期限と方法
個人事業主にとって確定申告は重要ですが、申告には期限があります。ここでは、確定申告の期限と申告の方法について見ていきましょう。
提出期限の日程について
確定申告では、確定申告書を作成し税務署へ提出します。確定申告書の提出期間は、原則、2月16日から3月15日までです。令和6年分の確定申告の場合、確定申告書の提出期限は令和7年3月17日になります。その年により、確定申告書の提出期限は曜日などによって前後することがあります。また、還付申告(税金の還付がある場合)の場合は、2月15日以前でも提出できます。
確定申告の方法(e-Taxや書類提出など)について
確定申告書の提出方法には、次の3つがあります。
1.e-Tax
確定申告の方法のひとつに、e-Taxがあります。
e-Taxとは、電子申告によって確定申告書を提出する方法のことで、申告書を紙ではなくデータとして提出します。原則、24時間受付をしているので便利です。
e-Taxを行う方法として、会計ソフトと連携している専用ソフトを使う方法や、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法など、さまざまな方法があります。現在は、確定申告書等作成コーナーを利用する方法が一般的になっています。
e-Taxをする方法によっては、事前に税務署の許可が必要となるケースがあるので、注意しましょう。
2.税務署の窓口で提出する
確定申告では、e-Taxではなく、紙の確定申告書を作成し、税務署の窓口に提出することが可能です。税務署の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。ただし、税務署によっては、確定申告期間中の一部の日曜日に受付を行っていることもあります。開庁時間外の場合でも、時間外収受箱に確定申告書を投函することが可能です。
なお、確定申告書を紙で提出する場合は、確定申告書の控えも一緒に持参する必要があるので、注意しましょう。
3.郵送で提出する
紙の確定申告書は、郵送で提出することが可能です。郵送での提出先は所轄の税務署です。一部の税務署では、複数の税務署の事務を一括して行う業務センターが設置されていることがあります。その場合は、業務センターに郵送で確定申告書を提出することも可能です。
確定申告書は「郵便物」(第一種郵便物)もしくは「信書便物」として送付します。一般的には。簡易書留で送付することが多いです。郵送で確定申告書を提出する場合、消印(通信日付印)の日付は提出日とみなされます。
また、郵送の場合は、確定申告書の控えと返信用の封筒(切手貼付済のもの)も一緒に送付する必要があります。
【参照ページ】
申告と納税|国税庁
申告書の提出方法|国税庁
【税務署の開庁時間】|国税庁
確定申告に必要な書類の一覧
確定申告をするにあたり、所得の種類や個人事業主かどうかなど、納税者の状況によって必要な書類が異なります。確定申告で必要な一般的な書類は、次の通りです。
・確定申告書第一表・第二表
・確定申告書第三表(不動産の売却などがある場合)
・確定申告書第四表(損失申告の場合)
・青色申告決算書(青色申告の場合)もしくは、収支内訳書(白色申告の場合)
・各種控除証明書(生命保険控除や医療費控除などの控除を受ける場合。データでの提出が可能なものもあり)
・マイナンバーカードなど
【参照ページ】
〔令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類|国税庁
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
各書類の詳細と入手方法
確定申告で必要な書類は、書類によって入手方法が異なることがあります。確定申告で必要な書類の詳細と入手方法は、以下のとおりです。
| 確定申告で必要な書類 | 詳細 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 確定申告書第一表・第二表 | 納める税額の計算を行う確定申告の基本的な書類。原則、どんな人でも必ず提出する | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| 確定申告書第三表(分離課税用) | 土地や建物の売却、株式の売却などがあった場合などに必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| 確定申告書第四表(損失申告用) | 青色申告をしている場合などで、損失申告をする場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| 青色申告決算書 | 1年間の売上や経費、所得金額などを計算するための書類。青色申告をしている場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| 収支内訳書 | 1年間の売上や経費、所得金額などを計算するための書類。白色申告をしている場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| 各種控除証明書 | 控除を受ける内容により、必要書類が異なる。 | 原則、加入している保険会社などから入手する。医療費控除を受ける場合の医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書などは、税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |
| マイナンバーカードなど | マイナンバーについて、本人確認が必要となるため、マイナンバーカードの提示もしくは写しの添付が必要。マイナンバーカードがない場合は「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要。 | 各自治体など |
【参照ページ】
〔令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類|国税庁
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
所得の計算方法
個人事業主が納税金額を計算するためには、所得金額を求める必要があります。所得金額を求めるためには、経費の計算が重要です。しかし、経費の計算(計上)には注意点もあります。
ここでは、個人事業主の所得計算方法や経費の計算・注意点について見ていきます。
個人事業主の所得計算方法について
個人事業主が計算しなければならない所得として「所得金額」と「課税所得金額」の2つがあります。
所得金額とは、簡単にいうと事業の「もうけ」を表すものです。一方、課税所得金額とは、税額を求める基となる所得金額のことです。それぞれの所得金額の計算方法は、下記のようになります。
・所得金額
【所得金額=売上(収入)金額-必要経費(-青色申告特別控除額)】
所得金額とは、簡単にいうと、1年間の売上から経費の金額を差し引いたもうけのことです。青色申告をしている場合は、最大65万円の青色申告特別控除額をさらに差し引くことができます。
例えば、1年間の売上金額500万円、必要経費200万円、青色申告特別控除65万円の場合の所得金額は、次のようになります。
所得金額=売上金額500万円-必要経費200万円-青色申告特別控除額65万円=235万円
・課税所得金額
所得税の金額は、課税所得金額に所得税率を乗じて計算します。そのため、課税所得金額は税額を求める基となる所得金額になります。
【課税所得金額=所得金額-所得控除額】
課税所得金額は、所得金額から基礎控除や生命保険控除などの所得控除の金額を差し引いたものです。
経費の計算方法と注意点
所得金額は、売上金額から必要経費を差し引いて計算します。経費が多ければ所得金額が低くなり、納める税金も低くなります。逆に、経費が少なければ所得金額が高くなり、納める税金は高くなります。そのため、いかに経費を計算するかが重要です。
経費の計算は1年間にかかった経費を集計しますが、個人事業主の経費になるものは事業に関係する支出のみです。例えば、事業についての知識をつけるための書籍は経費になりますが、プライベートで楽しむ雑誌は経費になりません。
個人事業主の場合、同じお店でプライベートの商品と事業で使う商品を購入するなど、プライベートの支出と事業に関係する支出を一緒に支払うこともあります。そのような場合は、事業に関係する支出を分けて帳簿付けをするなど、事業の支出がどれで、いくらの金額なのかを整理しておかなければなりません。プライベートの支出まで経費にしてしまうと、後に税務調査で否認され、延滞税などのペナルティが課される可能性があるので、注意しましょう。
また、自宅で仕事をしている場合の電気代などのように、プライベートの支出と事業に関係する支出を一緒に支払っている場合は、仕事をしている時間など、適切な基準で経費を案分する必要があります。
【参照ページ】
所得税のしくみ|国税庁
控除と税額控除
経費と同様に、所得金額を低くするものが「控除」です。控除には、所得控除と税額控除があります。控除は納める税額の計算に影響を与えますが、所得控除と税額控除では、何から控除できるのかが異なります。
ここでは、所得控除と税額控除について見ていきましょう。
控除とは何かの説明
控除とは、一定の要件を満たした人が受けることができる、所得金額を減額できる項目です。個人事業主には、扶養家族がいるケースや保険を多く支払っているケースなど、その人によって置かれている状況や事情が大きく異なります。
その人の状況などを無視して、税金を一律で課してしまうと、税の平等が損なわれる可能性がでてきます。そこで、その人の状況などに応じて、一定の控除を設けて、税の平等を担保しています。これが、所得控除や税額控除などの控除です。
主な控除の種類(経費控除、特別控除など)と条件
所得税において代表的な控除として、所得控除と税額控除の2つがあります。それぞれについて見ていきましょう。
・所得控除
所得控除とは、売上金額から必要経費を差し引いて求めた「所得金額」から、さらに差し引く控除のことです。課税所得金額を求めるために使用します。所得控除には、次のものがあります。
| 所得控除の種類 | 内容・条件 |
|---|---|
| 雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けたときに受けられる控除 |
| 医療費控除 | 医療費を多く支払った場合に受けられる控除 |
| 社会保険料控除 | 健康保険や国民年金・厚生年金保険など、社会保険を支払った場合に受けられる控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った場合に受けられる控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合に受けられる控除 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に受けられる控除 |
| 寄附金控除 | 一定の団体などに寄付をした場合に受けられる控除 |
| 障害者控除 | 納税者本人や生計を一にする配偶者や扶養家族が障碍者の場合に受けられる控除 |
| 寡婦控除 | 納税者本人が寡婦であるときに受けられる控除 |
| ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親であるときに受けられる控除 |
| 勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生であるときに受けられる控除 |
| 配偶者控除、配偶者特別控除 | 一定の条件にあてはまる配偶者がいる場合に受けられる控除 |
| 扶養控除 | 扶養家族がいる場合に受けられる控除 |
| 基礎控除 | 納税者本人に対する控除 誰もが控除を受けることができる |
・税額控除
税額控除とは、納める税金から直接差し引くことができる控除のことです。所得控除よりも、節税効果が高いものになります。
一般的に、所得控除よりも利用される頻度は低いです。
税額控除でよく使われるものとしては、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)や、政党や認定NPO法人などに対する寄附金などがあります。
・その他の控除
経費についても、売上から差し引くことができる控除としての意味合いを持ちます。また、その他にも、その人の状況に応じたさまざまな控除があります。
例えば、青色申告を行っている場合の青色申告特別控除や、土地や建物を売却した場合の特別控除などが挙げられます。
確定申告のポイントと注意点
次に、確定申告のポイントや注意点を見ていきましょう。
確定申告時によくある間違いと対策
確定申告によくある間違いとして、以下のようなものがあります。
・事業所得以外の所得の漏れ
個人事業主の場合、確定申告で事業所得を申告しますが、他の所得があれば、その所得についても一緒に申告が必要です。例えば、パートやアルバイトなどをしている場合の給与所得や、不動産を売却した場合の譲渡所得などが漏れることがあるので、注意しましょう。
・ふるさと納税の記載を忘れない
ふるさと納税をしている場合、ワンストップ特例として、条件を満たせば確定申告が不要なケースがあります。しかし、確定申告をする場合は、たとえワンストップ特例を利用していたとしても、寄附金控除として確定申告書に記載する必要があります。
・確定申告を間違えた場合の処理
確定申告を間違えた場合、期限内であれば正しい確定申告書を再提出します。最後に提出した確定申告書のみがその年の確定申告書として取り扱われます。期限後であれば、修正申告や更正の請求が必要です。
【参照ページ】
【申告が間違っていた場合】|国税庁
確定申告後の手続き
確定申告書の提出をすると、次は納税の手続きをする必要があります。税金の納税方法には、いくつかの種類があります。また、場合によっては税金の還付を受けることもできます。
ここでは、確定申告後の納税の手続きについて見ていきましょう。
確定申告後の納税について
所得税の納税期限は、確定申告の期限と同じく通常、翌3月15日までです。納税の方法には、次のものがあります。
・納付書による納付
税務署や金融機関の窓口で、納付書により納税します。
・振替納税
口座振替によって納税をします。振替納税による納税期間は3月15日ではなく、おおむね4月下旬まで(その年により日付は異なる)になります。振替納税を利用するためには、事前の届け出が必要です。
・ダイレクト納付
e-Taxを利用している場合は、口座引き落としによるダイレクト納付が利用できます。ただし、税務署または金融機関に事前の届け出が必要です。
・クレジットカードによる納付
国税クレジットカードお支払サイトを利用すれば、クレジットカードによる納付ができます。
・その他
その他、一定の要件を満たすことで、インターネットバンキングやATM、スマホアプリ決済などで納税することが可能です。
確定申告による返金や請求書の受け取り方法
予定納税や源泉徴収がされている場合など、事前に税金を納めていることがあります。この場合、医療費控除や住宅ローン控除などの控除が大きければ、税金の返金(還付)が行われます。税金の還付では、請求書などは必要ありません。確定申告書の還付銀行の欄に、銀行名や口座番号などの必要事項を記載すれば、記載された銀行に、後日返金がされます。税金の返金の時期は、税務署の混み具合にもよりますが、おおむね確定申告書提出から1か月程度です。
【参照ページ】
納税の方法|国税庁
確定申告に関するよくある質問
個人事業主で確定申告をする必要がある場合は、納める税金がある場合です。納める税金がない場合は確定申告が不要です。例えば、税金の還付がある場合や赤字の場合は、確定申告は不要です。
しかし、確定申告をしないと、税金の還付が受けられない、青色申告の場合は損失の繰り越しができないなど不都合が起こります。また、その年の所得金額を証明することができないため、銀行からの融資などが受けられません。
そのため、通常、個人事業主なら納める税金がなくても確定申告を行います。
確定申告の期限を過ぎてしまったら、速やかに確定申告をする必要があります。期限後であるからといって、特別な申告が必要なわけではなく、通常の確定申告書を提出します。
特に、納税を伴う場合は、延滞税などのペナルティが課される場合があるので、注意しましょう。
確定申告に必要な書類は、所得の種類などによって異なります。一般的には、次の書類が必要です。
・確定申告書第一表・第二表
・青色申告決算書(青色申告の場合)もしくは、収支内訳書(白色申告の場合)
・各種控除証明書(生命保険控除や医療費控除などの控除を受ける場合。データでの提出が可能なものもある)
・マイナンバーカードなど
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。