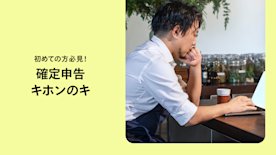確定申告の必要書類とは?3つの提出方法と添付書類、注意点

個人事業の確定申告では、1年分の収支を記帳した上で「確定申告書」や「決算書」などの必要書類を作成し、申告内容を証明できる添付書類を準備する必要があります。また、個人事業主だけでなく、会社員で年末調整を受けていても確定申告が必要な人、確定申告をする方がトクになる人もいます。
この記事では、個人事業主や会社員、パート、アルバイトなどで確定申告が必要な人や確定申告するのを迷っている人などへ、ケースごとに確定申告の必要書類や添付書類、提出方法をわかりやすく解説します。
確定申告の受付期間は、毎年原則2月16日から3月15日(3月15日が土日祝日の場合は後倒し)とされています。1ヵ月間しかない確定申告時期に慌てることのないよう、必要書類や添付書類の準備、提出方法について、しっかりと把握しておきましょう。
個人事業主の確定申告に必要な書類
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の二つの方法があります。ここでは、青色申告・白色申告ともに必要な書類と、それぞれに必要な書類について解説します。
青色申告・白色申告ともに必要な書類
(1)確定申告書
(2)本人確認書類
(3)所得を証明できる書類
(4)控除を受けるための証明書類
(5)還付を受け取るための口座番号
(6)印鑑は不要
それぞれ解説します。
(1)確定申告書
所得税の確定申告書様式は一つです。従来、確定申告書にはA・B2種類の様式がありましたが、令和4年分の申告から廃止となり、新様式に統一されました。確定申告書は第一表・第二表の2ページがセットになっており、様式はこちらからダウンロードできます。
提出方法は大きく分けて三つです。
・管轄の税務署、または確定申告会場へ持参する
・管轄の税務署へ郵送する
・e-Taxを利用してオンラインで送信する
e-Taxを使った確定申告にはいくつか方法があります。後述しますが、確認したい人は「確定申告書類の提出方法・e-Taxで提出する場合」をご覧ください。
(2)本人確認書類
確定申告を行うには、提出する本人であることを証明できる本人確認書類が必要です。
郵送または持参する場合
マイナンバーカードがある場合は、面と裏の両面をコピーして確定申告書に添付します。管轄の税務署に持参する場合はマイナンバーカードの提示のみで済むこともありますが、混み合うことなどを考慮すれば、あらかじめ写しを持参しておくと安心かもしれません。
マイナンバーカードを持っていない場合は「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方が必要です。どちらも一つずつ添付しましょう。
●番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類)
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
のいずれか一つ
●身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
・税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
のいずれか一つ
【参考ページ】国税庁PDF
e-Taxで確定申告する場合
e-Taxによる確定申告では、マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書とパスワードで本人確認を行います。また、マイナンバーカードを利用しないでe-Taxを行う場合は、税務署で対面による本人確認を行ったうえでe-Tax開始の手続きをします。
初めてe-Taxを利用して確定申告を行う場合は、e-Taxの開始届出書を所轄税務署に提出または送信して、16桁の利用者識別番号を取得する必要があります。
“e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーから取得した利用者識別番号を使用して確定申告書等作成コーナーで確定申告等を行う場合にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを使用せずID・パスワード方式での送信を希望される場合は、税務署で対面による本人確認を行い「ID・パスワード方式の届出」を行う等の手続きが別途必要です。”
(3)所得を証明できる書類
確定申告書には1年間の所得額を記入しますが、記入するために所得を証明できる以下のような書類が必要です。
個人事業主の場合
- 青色申告決算書(青色申告)、収支報告書(白色申告)
- 給与所得がある場合
- 源泉徴収票
- 報酬から源泉徴収されている場合(フリーランスやパラレルワーカーなど)
- 源泉徴収票、支払調書
- 株式などの配当について申告する場合
- 支払調書、特定口座年間取引報告書
(4)控除を受けるための証明書類
確定申告では、所得から差し引ける「所得控除」と、所得控除を差し引いて算出した税額から差し引ける「税額控除」が受けられます。控除を受けるためには、それぞれを証明できる証明書類が必要です。
- 所得控除の例…医療費控除、寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除など
- 税額控除の例…住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除など
- 確定申告書の第一表、左側の「所得から差し引かれる金額」欄に記載されているものが所得控除にあたります。所得控除については国税庁のページで確認してください。税額控除についてはこちらの国税庁ページをご確認ください。
控除を受けるために必要な書類については、「医療費控除や住宅ローン控除など控除申請に必要な書類」で詳しく解説しています。
(5)還付を受け取るための口座番号
確定申告書には、実際の納税額よりも多く納め過ぎた税金の還付を受け取るための口座情報を記載する欄があります。通帳などの受取口座がわかるものを用意して持参するか、確定申告書に記入しておきましょう。
確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に記入した銀行や郵便局などの口座に後日、還付金が振り込まれます。ここで記入した預貯金口座を公金受取口座に登録する場合は「公金受取口座の同意」欄に◯を記入します。※
すでに公金受取口座を登録している場合は「公金受取口座の利用」に◯を記入すれば、該当口座に還付金が振り込まれます。その際、口座情報を記入する必要はありません。
※注意点
”・確定申告書に申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)が正しく記載されていない場合や本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合は、公金口座を登録することはできません。
・書面申告手続きにおいて公金受取口座の登録申請を行う場合は、電子申告手続きに比べ、登録までに時間がかかる場合があります。
・公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできません。”
【引用】デジタル庁「所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法」
デジタル庁「よくある質問:所得税の確定申告手続における登録についてQ3-17」
(6)印鑑は不要
紙面による確定申告書を提出する際に必要だった押印は、令和3年度税制改正により不要となりました。それまで確定申告書第一表の氏名横にあった「印」の欄がなくなっています。
【参考ページ】国税庁「税務署窓口における押印の取扱いについて」
【その他の参考ページ】
【 国税庁】〔令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕 申告書に添付・提示する書類
e-Tax国税電子申告・納税システム「ID・パスワード方式とは」
青色申告に必要な書類
青色申告では、確定申告書のほかに「青色申告決算書」の提出が必要です。青色申告決算書には、一般用・不動産所得用・農業所得用・現金主義用の4種類の様式がありますが、事業所得の場合は一般用様式を使います。
青色申告決算書一般用は「損益計算書、損益計算書の内訳2枚、貸借対照表」の4枚構成になっています。
※初めて青色申告を行う事業者は、決められた提出期限までに青色申告承認申請書の提出が必要です。
白色申告に必要な書類
白色申告では、青色申告決算書の代わりとなる「収支内訳書」を提出します。収支内訳書にも一般用・不動産所得用・農業所得用の3種類がありますが、事業所得は一般用様式を使います。収支内訳書の一般用様式は、1枚目に売上・経費などを記入、2枚目に内訳を記入する2枚構成になっています。
共通の提出書類と保存書類
確定申告には提出する書類と保存が義務づけられている書類があります。
| 提出する書類 | 保存が必要な書類 |
|---|---|
| 確定申告第一表・第二表 | 源泉徴収票、支払調書 |
| 控除に必要な証明書類 | ・控除に必要な証明書類(提出省略可のもの)、所得税算出のための帳簿類、取引に関する書類(請求書・見積書・領収証など)、預貯金取引関係書類(事業用通帳など)、決算関係書類(棚卸表・賃金の内訳表など) |
控除を受けるために必要な証明書類は、控除の種類によって添付不要のものがあるほか、e-Taxで申告データを送信する場合に省略が認められているものがあります。詳しくは「添付書類に関する注意点」で解説します。
雇用形態別、確定申告に必要な書類
会社員の場合、通常は勤務先で年末調整を受けていれば確定申告が不要ですが、会社員やパート・アルバイトなどの雇用形態でも確定申告が必要なケースがあります。
■ 会社員・パート・アルバイトの確定申告
| 会社員で確定申告が必要な人 | パート・アルバイトで確定申告が必要な人 |
|---|---|
| 医療費控除など、年末調整以外の控除がある、給与以外の所得が20万円以上ある、2カ所以上から給与をもらっている、年の途中で退職した | 勤務先で年末調整を受けていない、パート・アルバイト以外で副業収入がある |
上記ケースをもとに必要な書類について解説します。ただし、共通して必要な書類については省略します。
■ 年末調整を受けていない、年末調整で控除されていないものがある
⑴会社員で医療費控除の申告をする人、年末調整に間に合わなかった控除がある際の必要書類
・源泉徴収票
・医療費の明細書(医療費控除の場合)
・控除を受けるための各種証明書類
⑵勤務先で年末調整を受けていないパート・アルバイトの確定申告に必要な書類
・源泉徴収票または給与明細書
・控除を受けるための各種証明書類
パート・アルバイト収入が年間103万円以下でほかに所得がなければ所得税はかかりませんが、毎月の給与から所得税が差し引かれている場合は所得税を払いすぎたままになってしまいます。勤務先で年末調整されていない場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付が受けられます。
■ 給与とは別に副業の収入がある場合
⑴年末調整された会社員、パート・アルバイトの必要書類
・源泉徴収票
・副業の支払調書
(ない場合は通帳・レシート・電子データなど収入や経費がわかるもの)
⑵年末調整されていないパート・アルバイトの必要書類
・源泉徴収票または給与明細書
・控除を受けるための各種証明書類
・副業の支払調書
(ない場合は通帳・レシート・電子データなど収入や経費がわかるもの)
■ 2カ所以上から給与をもらっている場合
⑴年末調整された会社員、パート・アルバイトの必要書類
・源泉徴収票
・年末調整を受けていない勤務先の収入状況がわかるもの(給与明細表や振込通帳など)
⑵年末調整されていないパート・アルバイトの必要書類
・控除を受けるための各種証明書類
・二つの勤務先の収入状況がわかるもの(源泉徴収票や給与明細表、振込通帳など)
■年の途中で退職した(退職年の12月31日時点で再就職していない場合)
・源泉徴収票
・控除を受けるための各種証明書類
・退職後に支払った国民健康保険や年金などの社会保険料の領収証
“所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。”
【引用ページ】国税庁「確定申告書作成コーナー・よくある質問」
確定申告の申告漏れや過少申告がある場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。また、実際の納税額以上に税金を払いすぎている場合は確定申告をすることで還付金を受け取れます。自分に該当するケースがないか把握して、きちんと確定申告を行いましょう。
【参考ページ】国税庁:家族と税「パート収入に対する税」
医療費控除や住宅ローン控除など控除申請に必要な書類
個人事業主だけでなく、会社員も年末調整では受けられない控除があります。また、寄付金控除や住宅ローン控除など、年末調整に間に合わなかった場合も確定申告をすることで控除を受けられます。
各種控除を申請するための書類はそれぞれ異なるので、ここでは主な控除を受けるために必要な書類を確認しておきましょう。
■ 社会保険料控除
申告する納税者自身や、生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を支払った場合、その金額が所得から控除されます。会社員の場合、年末調整で社会保険料控除の申告を忘れたときは確定申告をすれば控除を受けられます。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 国民年金保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金 | 納めた保険料の控除証明書、納付書や領収証書、QRコード付控除証明書の印刷書面(国民年金保険料)または電子的控除証明書(e-Taxの場合) |
■ 小規模企業共済等掛金控除
個人事業主が加入する小規模企業共済の掛金や、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入した場合は、その金額が控除の対象になります。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金) | 小規模企業共済等掛金証明書、iDeCoの掛金払込証明書 |
■ 生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料や地震保険料などを支払った場合は、一定の金額が控除されます。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 生命保険料、介護保険料、個人年金保険料、地震保険料 | 支払った掛金の控除証明書、支払掛金のQRコード付控除証明書印刷書面、または電子的控除証明書(e-Taxの場合) |
■ 雑損控除
自然災害や盗難などによって、「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる支出をした場合に受けられる控除です。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害。火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害。害虫などの生物による異常な災害。盗難。横領 | 災害などに関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書、保険金の補填額がわかる書類 |
■ 医療費控除
1年間でかかった医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合は、確定申告で医療費控除の対象となります。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 1年間でかかった医療費のうち実際に支払った金額のみが対象(保険金で補填、高額療養費で還付は除外)、生計を一にする配偶者や親族の合算適用(別居の場合も◯)、非課税は対象外 | 医療費控除の明細書、医療費通知(医療費のお知らせ)原本、医療費通知のQRコード付控除証明書印刷書面、または電子的控除証明書(e-Taxの場合)医療費通知の記載事項入力(e-Taxの場合)医療費の各種証明書、医療費の領収証(自宅保管が必要:5年間) |
■ セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
ドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品の世帯での年間購入費が、1万2,000円以上の場合にセルフメディケーション税制の利用が可能です。ただし、医療費控除を行う場合は利用できません。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 控除を受ける年に予防接種や健康診断などの健康のための取組をおこなっているとき利用可能 | セルフメディケーション税制の明細書、予防接種や健康診断の領収証や診断結果、対象となる医薬品のレシート(証明書) |
■ 寄附金控除
学校法人や特定の団体へ寄付したときは、寄附金控除の対象となります。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 公益法人や学校法人へ寄付したとき、政治献金をしたとき | 寄付金の受領証、寄付金控除に関する証明書、寄付金(税額)控除のための書類、寄付金の受領証、寄付金控除に関する証明書のQRコード付控除証明書印刷書面または電子的控除証明書(e-Taxの場合) |
■ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して自宅を購入したときや増改築したときなどに適用される控除です。会社員の場合、2年目以降は年末調整されますが、初めて適用を受ける場合は確定申告をする必要があります。その際は登記事項証明書や工事請負契約書など複数の契約書類の提出が必要ですが、2年目以降は以下の書類の提出となります。詳しくはこちらをご確認ください。
| 対象となるもの | 控除を受けるための必要書類 |
|---|---|
| 住宅ローンを利用して自宅を購入した、増改築したときなどで、2年目以降の控除を受けるとき | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、上記二つの書類のQRコード付控除証明書印刷書面または電子的控除証明書(e-Taxの場合) |
【参考ページ】
国税庁:申告書の提出
国税庁:控除証明書等の電子的交付について
国税庁:e-Tax・QRコード付証明書等作成システムについて
国税庁:住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
国税庁:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
確定申告書類の提出方法
確定申告書類の提出方法は「郵送する、直接持参する、オンライン(e-Tax)で送信する」三つの方法があります。それぞれの提出方法について確認しておきましょう。
■ 郵送する場合
確定申告書を郵送する場合は、住所地のある所轄の税務署へ送ります。確定申告書は「信書」にあたることから「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付する必要があり、小包や宅配便などの方法で送ることはできません。
確定申告書の提出には期限があります。郵送の場合、郵便物に押される消印(通信日付印)の日が提出日となるので、必要書類や添付書類の漏れがないよう、確実に申告期限の3月15日(土日祝日の場合は翌日)に間に合うように手続きを進めましょう。
■ 持参する場合
住所地の管轄税務署へ提出する場合は、窓口に書類一式を持参します。記入方法がわからない場合や質問がある場合は確認して提出できるのでおすすめです。税務署の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までですが、閉庁日でも時間外収受箱へ投函することで提出できます。また、一部の税務署では申告期間の日曜日に相談や受付を行う場合があるほか、管轄の税務署が行う確定申告会場へ持参する方法もあります。
■ e-Taxで行う場合
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、インターネットを通じて確定申告や納税の手続きを行うシステムです。e-Taxによる送信の方法は「マイナンバーカードを使って送信する方法」と「IDとパスワードを使って送信する方法」の二つがあります。
A. マイナンバーカードを使って送信する方法
マイナポータル連携を使えば、控除証明書のデータや医療費通知情報、公的年金などの源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書をまとめて取得して申告書へ自動入力できます。スマートフォンかパソコンを使って送信しますが、それぞれ必要なものが異なります。
| スマートフォンで申告する場合 | パソコンで申告する場合 |
|---|---|
| ・マイナンバーカード | |
| ・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン | ・マイナンバーカード |
| ・ICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン |
B. IDとパスワードで送信する方法
マイナンバーカードを持っていない人は「ID・パスワード方式の届出完了通知」を税務署で発行(対面による本人確認が必要)してもらえば、e-Taxで送信できます。詳しくはこちらをご確認ください。
【参考ページ】
国税庁:申告書の提出
国税庁:申告書の税務署への送付
国税庁:税務署の開庁時間
政府広報オンライン:令和4年分確定申告・便利なe-Taxをご利用ください!
添付書類に関する注意点
確定申告では、申告の内容を証明できる添付書類が必要ですが、制度変更に伴い提出不要となったものがあります。また、e-Taxを利用して確定申告書を提出する場合には、各書類の記載内容を入力することで提出または提示が省略できます。ただし、入力内容を確認するために税務署などから書類の提出や提示を求められることがあります。添付書類についても、法定申告期限から5年間の保管義務があるので必ず保管しておきましょう。
■ 提出不要の添付書類
平成31年4月1日以後の確定申告では、以下の書類の添付が不要となっています。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
■ e-Taxを利用すれば省略できる添付書類
以下の書類は、確定申告書の提出をe-Taxで行う場合、書類の記載内容を入力して送信することで税務署への書類の提出または提示を省略できます。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
-
(注1)令和3年分以降の所得税より、「医療費控除の明細書」に入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省略することができます。
(注2)平成29年分から令和2年分の所得税において、「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省略することができます。
(注3)平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に提出又は提示が不要となりました。
確定申告の必要書類に関するよくある質問
個人事業の確定申告には
(1)確定申告書
(2)本人確認書類
(3)所得を証明できる書類
(4)控除を受けるための証明書類
(5)還付を受け取るための口座番号
が必要です。ほかにも申告の方法や雇用形態、どの控除を受けるかなどケースに応じて必要な書類が異なるので、確認して準備を進めましょう。国税庁のHP「確定申告書等の様式・手引き等」のページからダウンロードして印刷できます。また、確定申告書の用紙は税務署や市区町村の担当窓口、相談会場や確定申告会場にも用意されています。e-Taxで確定申告する場合は「確定申告書等作成コーナー」からパソコンで手続きが可能です。
また、会計ソフトを使って確定申告をする場合は、会計ソフトの機能で申告書が作成できるものが多いので、利用している会計ソフトのマニュアルなどで確認してください。所得税の確定申告書・決算書などの必要書類のほかに本人確認ができるマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は通知カードや運転免許証などが必要です。詳しくは「個人事業主の確定申告に必要な書類⑵本人確認書類」を参照してください。還付金がある場合は銀行口座がわかるようにしておきましょう。
本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。