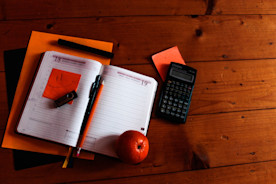フリーランスや副業、パラレルキャリアなど、働き方改革が進むにつれて、得意分野や持ち味を生かしてスモールビジネスを始める人が増えてきています。
収入を得ることで、気になるのは税金です。一定のまとまった収入には所得税がかかります。納税は義務ですが、できるだけ賢い納め方をしていきたいものです。
今回は、フリーランスや自営業などスモールビジネスで活躍している人向けに「所得控除とは何か」「所得控除にはどんな種類があるか」「所得控除を活用するにはどうすればよいか」について解説します。

所得控除制度とは
まずは、そもそも所得控除がどんなものなのか、制度の概要をみていきましょう。
ある程度の収入を得ると、所得に対する税金がかかり、これが所得税です。
所得控除は、所得税を納めることになる納税者の個別事情を考慮し、実際に税金を負担できる力に応じた税額となるように調整するために設定されています。
所得控除は、納税者の「応能負担」を図るために設けられている
所得控除は、納税者が個別の事情の中で担税力(税金を負担できる力)に応じた納め方ができるよう、納税者本人と扶養親族の状況や、医療費などの事情、生命保険などの社会的事情など、次の負担を考慮するものです。
・担税力への影響の考慮(医療費など)
・社会政策上の要請(保険や寄付など)
・個人的事情の考慮(障害者や寡婦・寡夫、勤労学生の有無など)
・課税最低限の保証(配偶者や扶養家族など)
たとえば、同じ年収だったとしても、扶養している家族がたくさんいる、長期に渡って医療を受けているなど、人によって生活にかけている出費が異なっています。このような個別の事情を「控除」として収入から差し引くことによって税金の負担の不均衡を解消するよう、「応能負担」という考えが反映されているのです。
参考:税務大学校講本 所得税法(平成30年度版)第5章 所得控除(国税庁)
控除には、所得控除と税額控除の2種類がある
所得税に関する控除は2種類あります。
大雑把にいうと、所得は「売上-経費」で求められ、所得税率は「所得-所得控除」の額に掛けられます。その後、算出された額に対する税額控除という控除を差し引いたものが、所得税になります。計算式にすると次のようになります。
納税額=(売上-経費-所得控除)×所得税率-税額控除
このように、所得税を算出する際、税率を掛ける前に差し引く所得控除と、税率を掛けた後で差し引く税額控除との二つの体制で、課税の負担を下げています。控除は自己申告なので、どの控除を使うのが最も適切なのかをよく見極めておく必要があります。
たとえば、認定NPO法人や公益社団法人などへ寄付した場合、寄附金控除の制度が使えますが、実はこの寄付金控除は、所得控除にも税額控除にも存在し、どちらで控除を受けてもよいとされています。
所得控除の種類
では、所得控除には、具体的にどのようなものがあるでしょうか。
所得税は現在、14種類に分かれており、目的別にみると、次のように分けられます。
担税力への影響の考慮:雑損控除、医療費控除
社会政策上の要請:社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
個人的事情の考慮:障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
課税最低限の保証:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
日本に住所等がある居住者の場合は14種類
日本国内に住所などがある居住者の場合は、14種類の所得控除を活用できます。
所得控除は、関係者の状況に係る「人的控除」と、社会的な出費などの「その他の控除」とに分けることができます。
下表に、基本的な人的控除、特別な人的控除について、控除の対象と控除額を整理しました。当てはまるものを確認し、確定申告のときに確実に控除できるようチェックしておきましょう。
基本的な人的控除

特別な人的控除

人的控除以外の所得控除について、どういう状況で適用されるかの概要を整理しました。それぞれの控除額の計算式については、国税局のホームページなどで確認してください。
その他の所得控除制度

請求書の作成から送信まで簡単スピード対応
Square 請求書は決済機能付きのクラウド請求書サービスです。無料ではじめられ、自動送信や定期送信など便利な機能も盛りだくさん。フリーランス、個人事業主、業務請負やサービス請負業の請求業務を簡単に効率化できます。
日本に住所等がない非居住者の場合の控除は3種類
参考までに、日本国内に住所などがない非居住者の場合、適用される所得控除は、人的控除では本人に係る「基礎控除」、その他の控除では「雑損控除」「寄附金控除」のみになります。
参考:No.1100 所得控除のあらまし(国税庁)国税庁

2020年からはフリーランス減税も始まる
税制度は、社会情勢などを合わせて変化しています。税に関する情報は、常に最新のものを確認するようにしましょう。
2020年1月に行われる所得税の見直しにより実施される「フリーランス減税」について簡単に整理しておきましょう。
この所得税の見直しは、働き方改革の一貫で、給与所得者とフリーランスとの働き方の違いによる税の負担の差をなくすために行われるもので、年収が850万円を超える会社員や1,000万円以上の年金を受け取っている人は増税となる一方、個人事業主やフリーランスは減税される見通しです。
基礎控除額の変更
所得控除の一つの基礎控除について、現在38万円が48万円に引き上げられるとされています。一方、高所得者の場合、所得が2,400万円を超えた段階から基礎控除の額が減りはじめ、2,500万円を超えると控除がなくなる見込みです。
給与所得控除額の変更
給与による収入がある人に関係する話です。
給与所得控除が10万円引下げられ、給与所得控除の上限額も現在の1,000万円から850万円になり、増税になる範囲の人が増えます。また控除の限度額も220万円から195万円に下がります。高額所得の人は増税となる見込みです。
青色申告特別控除額の引き下げ
フリーランス、個人事業主が青色申告をすると、現在65万円の控除がありますが、55万円に引き下げられます。ただし、これについては、e-Taxを使った申告にすると65万円のままの見込みです。
公的年金控除額の引き下げ
年金収入がある個人事業主やフリーランスに関係ある話で、控除額が10万円引き下げられます。また、年金の収入が1,000万円以上の場合に控除額の限度が195万5,000円となり、年金収入と給与の両方を受け取っている場合、控除が片方に制限されます。このため、年金収入が1,000万円以上の人や、給与などの所得が1,000万円以上の人は増税となります。
小規模企業共済等掛金控除は節税にもなる所得控除
フリーランスや自営業のサービス内容によっては、経費があまり発生しないうえに所得控除が適用される条件もあまりないという人も少なくありません。そのような人には、小規模企業共済等掛金控除の対象となる小規模共済や個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)に加入することを検討してみてはいかがでしょうか。
小規模企業共済等掛金控除のメリット
小規模企業共済等掛金控除は、社会保険料控除とよく似た所得控除で、小規模企業共済、確定拠出年金などが対象となります。
この制度のメリットは、年間に支払った掛金の全額が所得控除されるというところです。小規模企業共済や個人型確定拠出年金を活用することで、退職時の資金や年金の積立ができる上に、掛金を全額控除できるため、大きな節税になります。小規模企業共済と個人型確定拠出年金は併用することもできます。
小規模企業共済とは
フリーランスや個人事業主、小規模企業の役員などが事業をやめたり退職したりする際に、資金を準備しておくための積み立てを行う共済制度で、いわゆる個人事業の退職金代わりになる制度のようなものです。
掛金は月1,000円から70,000円まで500円きざみで選べ、途中で増額ができます(減額の場合は制限があります)。半年払いや年一括払いのしくみもあります。
共済金は、退職・廃業時に受け取ります。受け取り方法は一括も分割も選べます。一括の場合は退職所得、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制のメリットもあります。ただし、短い期間で解約した場合は元本割れします。
小規模企業共済のもう一つの特徴として、掛金の範囲内で事業資金の貸付けをしてくる制度があります。経営安定や傷病災害、新規事業展開など、いろいろな貸付けがあります。低金利で、即日貸付も可能と、心強い制度です。
参考:小規模企業共済 制度の概要(中小機構)中小機構
個人型確定拠出年金(イデコ)とは
確定拠出年金は、資産形成方法の一つである私的年金で、企業型と個人型があります。個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)は2017年から原則として20歳以上60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。
個人型確定拠出年金は、月5,000円から1,000円単位で掛金を設定でき、自営業の場合は国民年金基金または国民年金付加保険料との合算で月68,000円まで増額できます。
個人型確定拠出年金の運用方法は自分で商品を組み合わせます。リスクと利回りをみながら運用商品を変更するなど、自分で資産を増やしていくことができます。一般の金融商品だと運用の際に課税されますが、個人型確定拠出年金は非課税です。
また、60歳で老齢給付金を受け取ることができるのですが、そのときに年金か一時金かの受け取り方法を自分で決めることができます。年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除の対象となるため、節税になります。
執筆は2019年8月8日時点の情報を参照しています。
*当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。
*Photography provided by, Unsplash